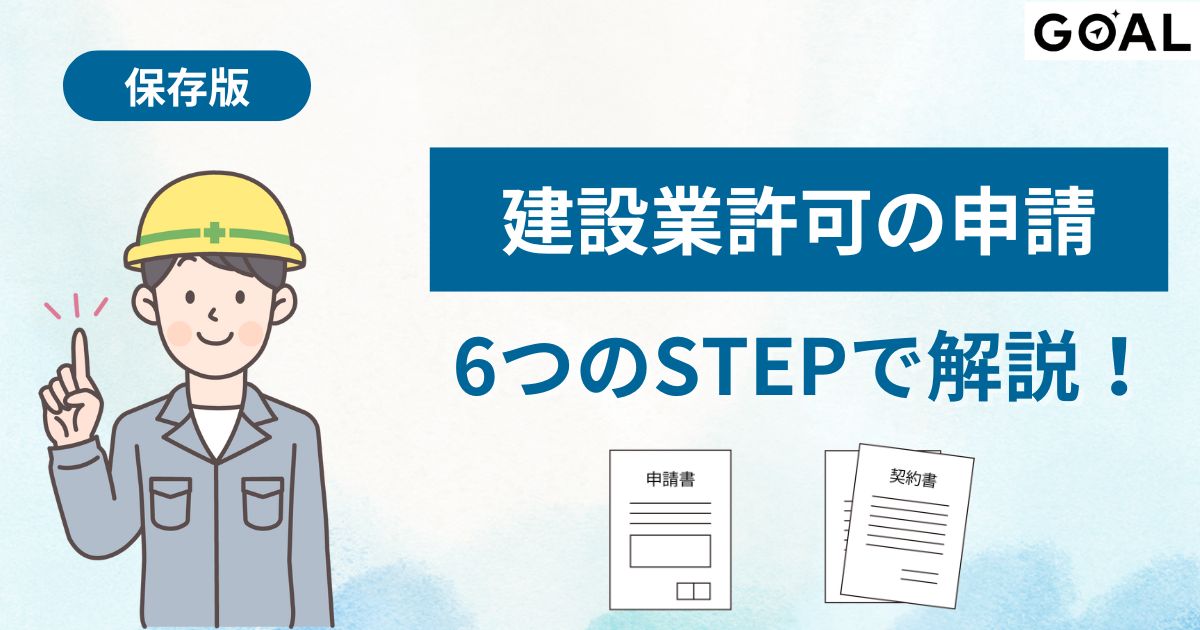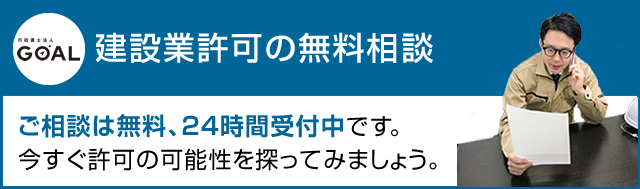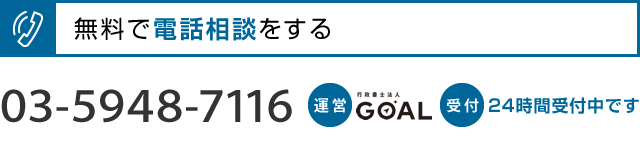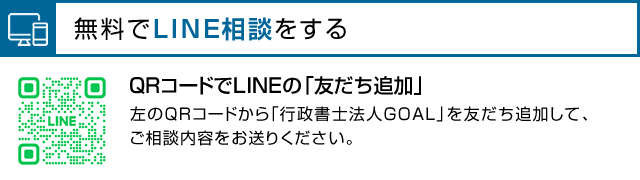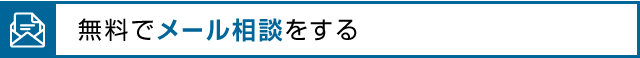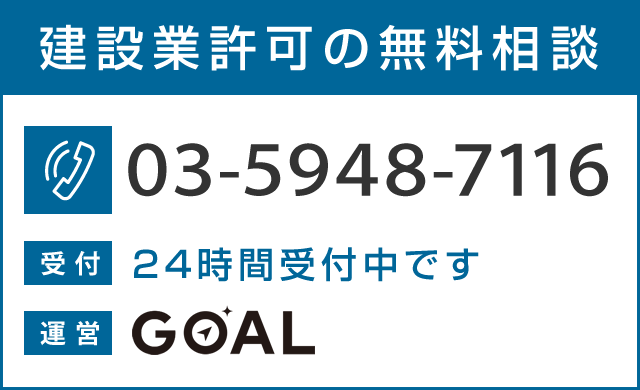建設業を始めるにあたって必要になるのが建設業許可です。
しかし申請方法や必要書類、申請の流れなど、初めての方には分かりづらいことも多いものです。
今は必要ではなくても、いつ許可が必要な大きな案件が入ってくるかわかりません。
建設業者は早いうちに許可の基本を押さえておくと安心です。
今回はこれから建設業許可を取得したい方、基本を学んでおきたい方向けに、申請方法や流れ、注意点を分かりやすく解説します。
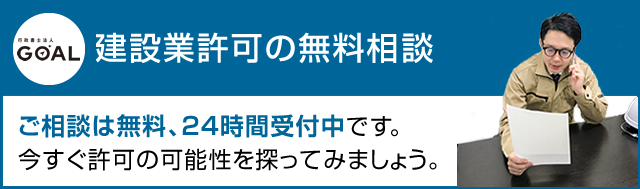
- 上場企業や大手グループへのサポート実績多数!複雑な状況もお任せください
- 簡単なヒアリングで建設業許可の取得可能性の判断をお伝えします
- 許可要件を満たさない場合は、最短取得までの準備方法をご案内いたします
目次
建設業許可の申請の流れ
許可を取得するには、様々な要件を満たさなくてはなりません。また提出する書類はたくさんあり、その準備には労力と時間がかかります。
許可がとれるまでやるべきことを一つずつ確実にクリアをしていく必要があります。
- 許可要件を満たすか確認する
- 必要書類を揃える
- 申請書を作成する
- 申請書を提出する
- 審査をうける
- 結果通知の受領
では申請の流れについて説明していきましょう。
許可要件を満たすか確認する
まず、建設業許可が必要かどうかの確認をしましょう。
建設業許可が必要になるのは、工事1件の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)になる場合です。
これ未満であれば「軽微な工事」として許可なしでも施工が可能です。請負金額500万円の判断は自己判断ではなく客観的な事実をもって決定されます。
許可が必要な工事を無許可で行うと建設業法違反となり、行政処分や罰金の対象になる可能性があります。
また信用問題にも関わるため、取引先からの信頼を失うこともあります。
許可が必要であれば、以下の要件を満たすかどうかを確認します。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
- 営業所技術者等(専任技術者)
- 財産的基礎要件
- 誠実性
- 欠格要件
常勤役員等(経営業務の管理責任者)
建設業許可が必要になったら、最初に確認するべきことが「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」がいるかどうかです。
許可を取るためには、建設業の経営に5年以上携わった経験がある役員を「常勤役員等」として置く必要があります。
通常、法人であれば取締役や令3条使用人、個人事業主であれば本人や支配人が常勤役員等としておかれます。
この要件は非常に難しく、ここで許可をあきらめる業者もいるほどです。
しかし、年数を経ることで要件を満たしたり経管認定という作業を経て認められる場合もありますので、すぐに諦めずに精通した専門家に相談するのが良いでしょう。
営業所技術者等(専任技術者)
次に重要な要件は、「営業所技術者等(専任技術者)」です。
許可を取得したい業種に応じた資格や実務経験を持つ常勤の技術者を、各営業所に1名以上配置する必要があります。
営業所技術者がいない営業所は許可がとれないので、その営業所では500万円以上の建設工事を契約することはできません。
建設業許可は、下請に出す場合においての契約金額に応じて「一般建設業」と「特定建設業」のどちらかとなります。
そして、それぞれ必要な専任技術者を「営業所技術者等」、「特定営業所技術者等」と呼びます。
営業所技術者等は、他の営業所と兼務することはできません。
また、一人の技術者が複数の資格を持つ場合などは、資格要件に満たせば一人で複数業種の営業所技術者等になることもできます。
財産的基礎要件
一定の自己資本や流動比率を確保していることも、建設業許可の要件です。
建設業を行うには、機械器具や建設機械の所有、必要数の労働者、資材などのために資産を確保している必要があります。
財産的基礎要件は下記のものとなります。
- 自己資本の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間に建設業許可業者であったこと
具体的には、申請直前の決算において貸借対照表の純資産合計の額(自己資本)が500万円以上あること、申請時に残高が500万円以上の申請者名義の口座があることなどです。
特定建設業の場合はさらに次の要件が必要です。
- 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金の額が2,000万円以上あること
- 自己資本の額が4,000万円以上
個人・法人どちらもこの金額要件は同じです。
財務面の要件は見落とされがちなので注意しましょう。
誠実性
建設業法第7条第3号において、誠実性についての要件が示されています。
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
ここでいう「不正な行為」とは法律に反する行為であり、「不誠実な行為」とは請負契約に反する行為をいいます。
役員は、登記簿上の取締役は当然のこと、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主や、個人で出資総額の100分の5以上にあたる額を出資している人も該当します。
この誠実性については、宅建業法や建築士法の規定により不正または不誠実な行為で免許取り消し処分を受けた者がその処分より5年を経過していない場合も適用されます。
欠格要件
欠格要件は下記のとおりです。
- 破産者で復権を得ないもの
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
役員等に欠格要件に該当する人がいる場合は、建設業許可を取得することはできません。
必要書類を揃える
要件を満たすことがわかったら、次は申請先の確認です。
許可の申請先は、「常勤役員等」が常駐している営業所がある都道府県となります。
この常勤役員等がいる営業所を「主たる営業所」と呼びます。主たる営業所は必ずしも本社であるとは限りません。
また、複数の都道府県に許可を持つ営業所を置きたい場合は、都道府県知事許可ではなく、国土交通大臣許可となります。
営業所が建設業許可を持っていると、その営業所で建設工事に関わる請負契約の締結など建設業に関わる実質的な業務が行えます。
申請先の確認ができたら、必要書類を揃えます。
申請先によって揃える書類や提出方法が異なりますので、最初に手引きを確認しておくようにしましょう。
主に必要な申請書類は下記のものです。
- 建設業許可申請書
- 申請書別紙一【役員等の一覧表】
- 申請書別紙二【営業所一覧表】
- 申請書別紙三【証紙貼付用紙】
- 申請書別紙四【専任技術者一覧表】
- 使用人数
- 誓約書
- 健康保険等の加入状況
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 主要取引金融機関名
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 営業所技術者等(専任技術者)証明書
- 許可申請者の住所、生年月日当に関する調書
主な確認書類は下記のものです。
- 工事請負契約書の写し
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 住民票
- 常勤役員等及び専任技術者の常勤性の確認資料
- 健康保険等の加入状況の確認資料
有効期限のある書類もありますので、取得時期に注意しましょう。
個人事業主の場合に必要な書類
個人事業主が建設業許可を取得したい場合、以下の書類が追加されます。
- 事業税納税証明書
- 個人確定申告書の写し(直近決算)
個人であっても申請手数料等は法人と同額となります。
法人の場合に必要な書類
法人の場合はさらに下記の書類が必要です。
- 登記事項全部証明書(法人の場合)
- 定款
- 法人税納税証明書
- 株主調書
- 役員等の一覧
住民票や登記されていないことの証明書などは、役員全員分を取得しなければなりません。
本籍地が遠隔地である場合などは取得に時間を要しますので、注意してください。
特定と一般で異なる書類
「特定建設業」は元請として1件が5,000万円以上の工事(建設一式工事の場合は8,000万円以上)を下請に出す場合に必要な許可です。
特定建設業を取得するためには財産要件や技術者要件が一般建設業より複雑になります。
準備する書類に大きな違いはありませんが、特定の場合は営業所技術者等の資格が一級施工管理技士や一級建築士、もしくは指導監督的実務経験を有する人でなくてはなりません。
特定建設業を取得する場合は、これらの資格証明書等を添付する必要があります。
また、初回申請時もしくは更新時において直前決算で財産的要件が満たされていないと特定許可がとれませんので、日ごろから財産管理に気を付けておく必要もあります。
申請書を作成する
申請書類は、決められた様式に沿って記入します。
基本的な作成方法は同じですが、細かい点で地域ルールがありますので作成時には申請先の手引きを確認することをおすすめします。
手引きには詳細な記載例が載っていますので、こちらを参考にするとよいでしょう。
イレギュラーな場合や不明な点があれば、申請先に確認をしながら準備を進めましょう。
不備があると再提出が必要になるので、慎重に作成する必要があります。
従来の紙申請のほかに、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請が推進されています。
JCIPを利用するには、GビズIDプライムの登録が必要です。
国税庁や法務省、登録経営分析機関と連携しているので、JCIPを利用して申請することで書類の添付の手間が省けるものがあります。
また、JCIPで継続して申請をすることで過去の情報が電子保存されますので、再度書類を提出しなくてもよい場合があります。
自社の状況にあった作成方法を選ぶとよいでしょう。
申請書を提出する
書類の準備が整ったら、申請先の担当窓口に提出します。
直接役所に提出する他、郵送申請や電子申請(この場合は書類作成もすべて電子で行うこと)も可能です。
郵送申請の場合は、細かい提出ルールがありますので、事前に調べておきましょう。
許可申請書類は個人情報のものが多く、万が一の紛失に備えて書留やレターパックなど履歴の残る郵送方法で行います。
書類に不備があると連絡が来ますので、答えられるように提出した書類は写しをとって手元に保管しておいたほうが良いでしょう。
東京都の場合、新規申請は郵送で行うことはできません。
申請は一度で完了する事はあまりなく、書類の不備や不足が見つかることが非常に多いものです。
提出した申請書に受付印がもらえるまでは、何度もやり取りをする必要があります。
申請先には都道府県と国がある
建設業上の営業所の所在地が1つであれば、都道府県知事の許可となります。
複数の都道府県に営業所がある場合は、国(国土交通大臣)への申請となります。
建設業許可申請における「新規申請」とは、有効な建設業許可をどの都道府県からも受けていない状態で行う申請です。
すでに許可を有しており、他の都道府県でも許可が必要となった場合は、知事許可を二つ持つのではなく「大臣許可」に「許可換え得申請」をすることとなります。
この時、許可権者が変わりますので許可番号も変わります。
例えば、本社が東京にあり常勤役員等が常勤する支店が大阪であれば、申請先は大阪府となります。
この場合は建設工事に関わる契約行為は大阪の営業所で行い、東京本社で契約を締結することはできません。
また、営業所技術者等も大阪の営業所に常駐する必要があります。
さらにこの場合において、東京の本社に役員・営業所技術者等が常勤していて本社でも契約行為をする場合は、近畿地方整備局にて大事許可申請を行います。
申請にかかる費用と納付方法
新規申請では、都道府県知事許可の場合で9万円、国土交通大臣許可では15万円の申請手数料がかかります。
一般建設業または特定建設業のどちらも同時に申請する場合は、知事許可で18万円、大臣許可で30万円となります。
納付方法は自治体によって異なり、現金納付・収入証紙・電子決済などがあります。
JCIPを利用した電子申請の場合は「Pay-easy(ペイジー)」決済となります。
事前に管轄の窓口に確認しておきましょう。
審査をうける
申請書を提出すると、窓口にて書類の不備や不足などが確認されます。
書類を受け取れる状態になるまでは受付印をもらうことはできません。場合によっては何度もやり取りをする必要もあります。
受付印をもらえたら、ここから許可権者による審査が始まります。
審査を受けている間に不足や不備がみつかることもあり、この場合は補正対象となります。
標準処理期間が都道府県別に定められており、通常は30日〜45日ほどで審査結果が通知されます。
結果通知の受領
審査が終了し許可が下りると、許可通知書が発行されます。
郵送の場合は主たる営業所宛てに許可通知書が送られてきますので、必ず受け取れるようにしておきましょう。
土木事務所等に直接取りに行く都道府県もあります。その際には身分証明書の提示が必要になることもあります。
さらに電子申請をした場合は、電子で発行されることもあります。申請先によって受け取り方法が異なりますので、事前に確認をしておきましょう。
紙の許可通知書は一度発行されると次の更新まで再交付されません。
紛失しないように気を付けましょう。
書類作成時のよくあるミスと対策
書類の準備にあたっては手引きをよく見ながら行うことが大切です。
提出時に不備がみつかると実際に作り直さなげればならない場合があります。
実際にあったミスの例とその対策を挙げてみましょう。
- 氏名が住民票や登記簿謄本の表記と一致していない(特殊な漢字に注意すること)
- 住民票に本籍地が記載されていない(取得時に確認すること)
- 営業しようとする建設業の有資格者コードが違う(一覧表を確認すること)
- 工事経歴書の記載方法が間違っている(手引きを見ながら作成すること)
- 税込表記、税抜表記が混在している(作成した財務諸表に合わせること)
- 使用人数の数が違う(建設業に関わる従業員数を記載すること)
- 常勤役員等の経験年数が違う(確認資料で証明できる年数を記載すること)
- 実務経験証明書の年数が違う(カウント方法は都道府県により異なる)
- 証明書類の期限が切れている(申請時において取得してから3カ月以内)
- 許可を取りたい業種ではない工事契約書を添付している(業種を確認すること)
- 確認書類の監理技術者資格者証の期限が切れている(更新が必要)
これらは申請する都道府県によって対応が異なります。
わからないことは早めに確認をしたり、事前にチェックリストを作ることでミスが防げるでしょう。
建設業許可の申請は自分でできる?
建設業許可の申請は大変ではありますが、ひとつずつ段階を踏めば自分で申請をしても取得ができます。
時間も労力もかかりますが、自分で申請する業者は実際とても多いです。
どのような書類が必要か、どうやって作成すればよいかを一度しっかり確認しておくことで、変更届や次の更新申請時にその知識が役に立つはずです。
自分で許可申請に必要な書類をまとめることで、過去の膨大な書類の整理や必要な書類のファイリングを改めてできるかもしれません。
しかし、時間や自信がなければ行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
費用がかかりますが、精通した行政書士であればスムーズに審査が進むでしょう。
また、法改正やイレギュラーな対応にも柔軟に対応してくれます。