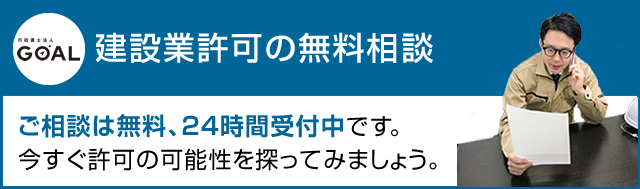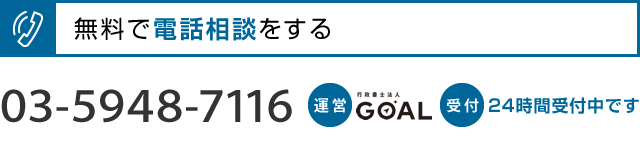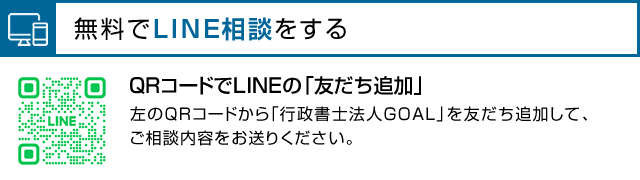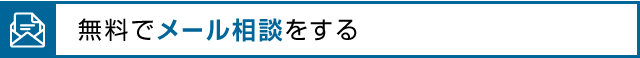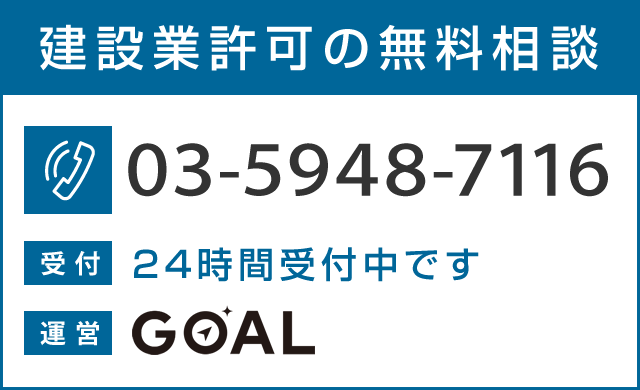建設業の中でも特に幅広い工事に対応する「とび・土工工事業」は、仮設足場や鉄骨の組立てや掘削・埋め戻し、地盤改良など多岐にわたる作業を担います。
この業種で事業を営むには、建設業許可の取得が必要になる場合があります。
しかし、「どこまでが許可の対象か」「他の業種とどう区別されるのか」など、制度の理解に戸惑う方も多いのが実情です。
今回は「とび・土工工事業」の建設業許可に焦点をあて、工事の内容や許可が必要なケース、取得要件をわかりやすく解説します。
目次
とび・土工工事業とは
とび・土工工事業とは、建設業法で定められた29業種の中の専門工事のひとつです。
最新の調査結果によると、2025年3月末時点で建設業許可業者の数は約48万社で、その中でもとび・土工工事業は最多の約18万業者となり、全体の約38%を占めています。
建設工事の現場において基礎工事の重要な役割を担うのがとび土工工事であり、「地面の上と下」「建物を建てる前段階」がその範囲となっています。
とび土工工事は多くの建設工事の初期段階で行われるため、基本的かつ不可欠とされることが多くなります。
特に近年は、高所作業における安全管理の重要性が増しており、とび職の高度な技術と経験が求められるようになっています。
工事の具体例
とび・土工工事業の代表的な工事内容には以下のようなものがあります
- 仮設足場の組立・解体(枠組足場、単管足場、吊り足場など)
- 鉄骨建方(鉄骨の組立、ボルト締め、仮締め本締めなど)
- 土工事(掘削、埋め戻し、盛土、敷き均しなど)
- 山留め支保工(H鋼、矢板の打設・撤去、地中梁構築など)
- 地盤改良(表層改良工、柱状改良工、深層混合処理など)
- 仮囲いや仮設フェンスの設置
- プレキャスト部材(PC板)の取り付け
- 重機誘導や荷受け
また、高層建築に伴う高所鉄骨工事、玉掛け・合図・荷重計算等による安全確保なども求められており、とび土工工事の需要はさらに広がりつつあります。
鳶と足場工事の違い
一般的に鳶といえば足場というイメージがありますが、実際にはとび職とは高所作業を専門とする職人の総称です。
鳶にはいくつかの分類があり、「足場鳶」「鉄骨鳶」「重量鳶」などが存在します。
中でも「足場鳶」は、建物の外周に仮設足場を組み立てたり解体したりする仕事を担当します。
そのため、足場工事は鳶職の仕事の一部という位置づけになります。
建設現場全体の立体的な構成や安全導線の設計に関わる作業もあり、鳶職人は非常に専門性の高い作業が求められます。
躯体の高さや規模に応じた足場設計、動線の確保、安全帯フックの配置なども行います。
一方、足場工事は、建物の建築や改修をする際に必要な作業用の足場を設置する工事全般を指します。
建築現場での仮設材の組立に限定され、仮設計画や安全管理の知識も求められます。
足場工事を専門に請け負う業者も多く、必ずしも「鳶職人」が行うとは限りません。
つまり、「鳶」は職種、「足場工事」は工事内容であり、鳶職の中に足場工事を担う職人がいるという関係です。
建設現場の安全と効率を支える上で、どちらも重要なものとなっています。
紛らわしい工事とその違い
とび・土工工事業は建設業の中でも他の業種と区別がつきにくく、紛らわしいとされることがよくあります。
これはとび土工工事が広範で多岐にわたり、「土木一式工事」や「舗装工事」「鋼構造物工事」などの他業種と内容が重なる部分があるためです。
また、「外構工事」「造成工事」「土工事」など現場で使われる名称が法律上の業種区分と一致していないことが多く、誤って別の業種と認識してしまうこともよくあります。
次に、その内容を具体的に見ていきましょう。
ブロック塀の設置
ブロック塀の設置は、とび・土工工事業に該当する場合とそうではない場合があります。
仕上げ目的のモルタルやセメント塗り、ブロックの積み上げなどが含まれる場合は「左官工事業」となります。
コンクリートブロックやレンガを使用する構造物の築造、タイル貼りなど装飾的な要素が強い場合は「タイル・れんが・ブロック工事業」に分類されます。
基礎の掘削・埋戻し、簡易な基礎コンクリートの打設など、地盤に関する作業が含まれる基礎工事を伴う場合は「とび土工工事業」です。
また、とび土工工事におけるブロック塀の設置は、安全面の配慮から高さ1.2mを超える場合は構造計算や鉄筋補強などが求められるのでより専門性が高くなります。
コンクリート舗装
地番改良や床コンクリート、地盤に直接打設するコンクリート工事は「とび・土工工事業」の範囲です。
コンクリート舗装は、舗装前の地盤整備、掘削・埋戻し・路盤の整形などを含むことがあるため、下地処理を専門に行う場合にはとび土工工事業のj許可が必要となります。
しかし、アスファルト舗装やコンクリート舗装、ブロック舗装、道路舗装のような仕上げを含んだりライン引きなどの作業がある工事は「舗装工事業」の扱いになります。
大規模な道路整備舗装などの場合は、「土木一式工事業」と「舗装工事業」が必要になります。
フェンスや門扉の設置
ブロック塀の基礎上にフェンスや門扉を設置する場合、基礎部分はとび・土工工事であり、上物(フェンス)の取付は別の業種になることがあります。
特にアルミ製やスチール製など部材の性質によって業種が異なるのも注意が必要です。
金属製の大型フェンスの設置は「鋼構造物工事業」であり、軽量なアルミ門扉やフェンスの取り付けは「板金工事業」や「建具工事業」となる場合もあります。
これらの設置に伴う堀削や基礎工事のみであれば「とび土工工事業」で可となります。
土木工事業との違い
「とび土工工事業」と「土木一式工事業」は、名称が似ていることから混同されがちですが、その内容と役割には明確な違いがあります。
「土木一式工事業」は、道路・橋梁・河川・下水道などのインフラ整備を主な対象とするのに対し、「とび・土工工事業」は建築物や構造物の施工に関する仮設・基礎・高所作業が中心です。
「とび土工工事業」は個別の専門作業に特化していますが、「土木一式工事業」は複数の専門工事を統合して施工管理する総合工事業となります。
規模も大きく異なり、「土木一式工事業」は公共事業やゼネコンなどの大型案件が多く、「とび・土工工事業」は中小規模の建築現場で主に必要となります。
とび・土工工事業の建設業許可
建設業を営むうえで欠かせない「建設業許可」とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために国または都道府県から取得しなければならない許可のことです。
建設業法に基づいて定められており、元請・下請を問わず、請負金額が税込500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延床面積150㎡以上の木造住宅)の工事をする際には、原則として建設業許可が必要となります。
この許可制度は、施工体制の整った業者による適切な工事の実施や、公共・民間を問わず工事発注者の保護、そして建設業界全体の健全な発展を目的としています。
また建設業の許可取得には、次の要件を満たす必要があります。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
- 営業所等技術者(専任技術者)がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
これらの人的要件や財務的要件を満たす必要があり、建設業許可は簡単に取得できるものではありません。
営業所等技術者の要件
営業所等技術者(専任技術者)とは、建設業許可を取得する営業所ごとに配置が義務づけられる技術者のことです。
要件は次のようになります。
- 営業所に常勤であること
- 該当工事に関する資格・実務経験を有すること
その営業所に常勤し、許可を受けた業種の専門的知識・経験を有する必要があります。
営業所等技術者は他の営業所と兼任することはできません。
許可の新規取得時だけでなく、更新や業種追加時にも審査される重要な要件であり、営業所等技術者が不在になると許可要件を満たさなくなるため注意が必要です。
建設業許可には請け負う工事の規模等により一般建設業と特定建設業があり、営業所等技術者の資格要件は若干異なります。
また、その要件は業種ごとに決められており、主に学歴・実務経験・資格のいずれかにより判断されます。
要件を満たす資格
とび土工工事業における営業所等技術者の主な要件は次のようになります。
- 指定学科卒業+3〜5年の実務経験
- 10年以上の実務経験
- 建設機械施工技士
- 土木施工管理技士
- 建築施工管理技士
- 造園施工管理技士
- 技術士
- 技能士
- 基幹技能者
上記の国家資格においては一級、二級、技師補も該当します。
とび土工工事業では、解体工事や舗装工事、鋼構造物工事など他業種と業務内容が重複するケースが多くなります。
さらに、とび土工工事業の営業所等技術者になるために必要な資格は上記のように様々ですので、しっかりと工事内容や要件を確認しておくようにしましょう。
経営業務の管理責任者の要件
建設業許可を取得するためには、「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」を主たる営業所におく必要があります。
常勤役員等は、建設業の経営を統括管理する立場の者であり、建設業に関する十分な経営経験を有していることが求められます。
具体的な要件は以下のようになります。
- 建設業に関し5年以上の経営経験を有する者
- 建設業に関し経営業務管理者に準ずる地位として5年以上経営経験を有する者
- 建設業に関し経営業務管理者に準ずる地位として6年以上経営業務管理者を補助する業務に従じた経験を有する者
経営経験とは法人の役員、個人事業主、支店長などの立場であった経験となります。
また、2020年の法改正で大きく条件が緩和され、以前は建設業の経営経験が5年以上でなければならなかったものが、「補佐的業務の経験」でも可とされました。
とび・土工工事業に関するよくある質問
最後に、とび・土工工事業に関するよくある質問をご紹介します。
足場の組み立てだけでも許可は必要?
足場の組立作業でも、請負金額が500万円(税込)以上であれば建設業許可が必要です。
請負金額が税込500万円未満の足場工事や、自社の建築工事のために足場を設置する場合、足場材の貸し出しだけ行う場合などは許可が不要となります。
また500万円未満の工事だけ行う場合でも反復的に行うのであれば、実質的には建設業者と見なされることもありますので注意が必要です。
外構工事はとび・土工工事に含まれる?
外構工事が「とび土工工事業」に該当するかどうかは、その工事内容によって異なります。
「とび土工工事」の許可で行える外構工事もありますが、すべての外構工事がこれに該当するわけではありません。
たとえば、敷地の整地・造成、掘削や埋戻し、ブロック塀や擁壁の基礎工事など、土工や基礎的な作業が中心の工事については、「とび土工工事業」に明確に該当します。
また、フェンス支柱の基礎工事なども部分的に該当することがあります。
一方で、門扉やアルミフェンスの設置、カーポートやサンルームの設置といった工事は、「鋼構造物工事業」や「建具工事業」、「板金工事業」など別の専門業種に分類されます。
さらに、舗装工事は「舗装工事業」、植栽や庭づくりなどは「造園工事業」に該当します。
外構工事という用語は非常に幅広く多種多様な工種が含まれるため、建設業許可においては工事の実態を踏まえて該当業種を正しく判断することが重要です。
このように外構工事はその内容によっては複数業種の許可が必要となる場合もあるため、注意が必要です。
解体工事はとび・土工工事業の許可でできる?
解体工事をする場合は、基本的に「解体工事業」の建設業許可が必要です。
建物の取り壊しや撤去作業などが解体工事となりますが、その規模は様々です。
軽微な解体工事であれば許可は必要ありません。
しかし、税込500万円以上の解体工事については、「解体工事業」の許可が必要です。
かつて解体工事は「とび土工工事業」で包括的に扱われていましたが、専門性や安全対策の観点から分離され、建設業許可の業種の中でも一番最近に新設された業種として成立しています。
また、500万円未満の工事であっても建設業許可とは別に「解体工事業登録」が必要ですので、解体工事をする場合は事前に確認しておきましょう。