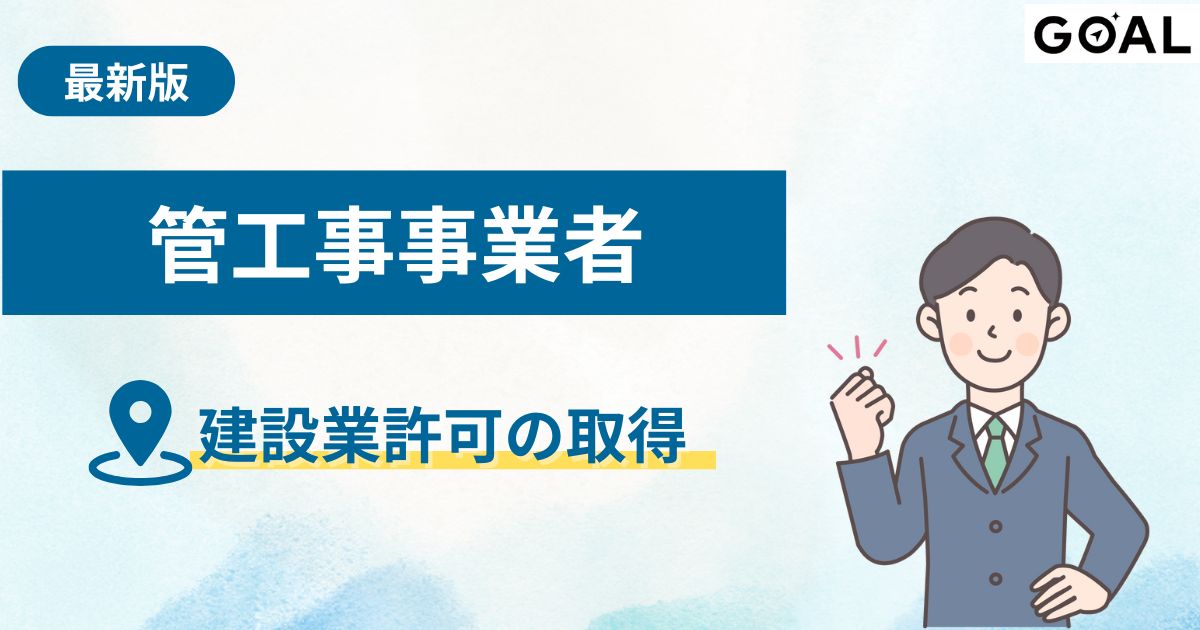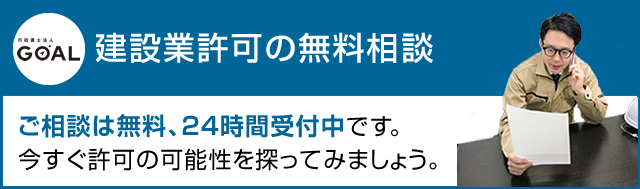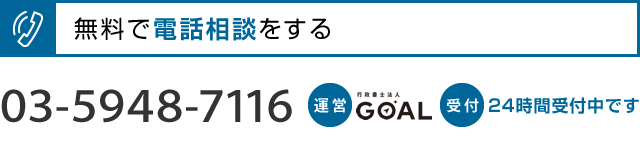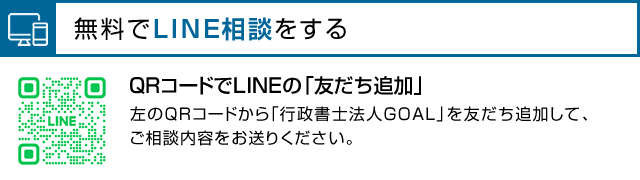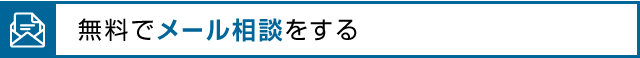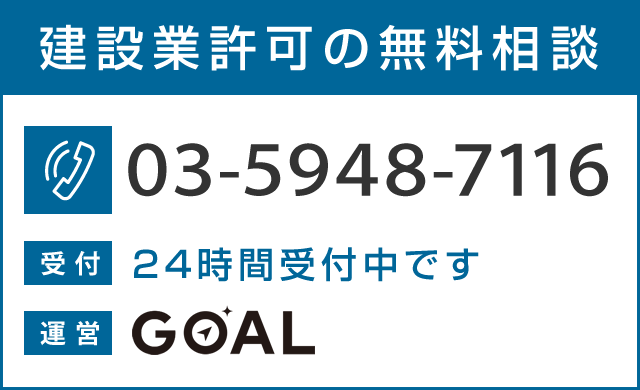建設現場で行われる「管工事」は、水道やガス、空調などの配管を取り付ける仕事です。
私たちの暮らしに欠かせないインフラ整備を担う管工事はとても大切な工事です。
これらの工事を一定規模以上で行うためには「管工事業」としての建設業許可を取得しなければなりません。
今回は管工事とは具体的にどのような工事なのか、また管工事に必要な許可や資格の種類について詳しく解説していきます。
目次
建設業許可における管工事業とは
建設業の中でも「管工事業」は、私たちの生活に直結する重要な役割を担っています。
給排水や空調、ガス設備などの工事は、住宅やオフィスビル、学校、病院など、あらゆる建物の快適さと機能性を支える不可欠なものです。
そして管工事の建設業許可を受けるには、決められた基準を満たす必要があります。
ここでは管工事業とはどのような工事を指すのか、許可取得の要件、紛らわしい工事の解説などをしていきます。
主な管工事の例
「管工事」とは、基本的に空調、給排水、ガス、冷暖房など、建物内外の配管設備に関する工事を指します。
具体的には下記のようになります。
| 給排水設備工事 | キッチンやトイレ、お風呂などで使う水を供給・排水するための配管工事 |
|---|---|
| 空調設備工事 | エアコンや換気扇など、室内の温度や空気の流れを調整する設備の設置 |
| ガス配管工事 | ガスコンロや給湯器などにガスを供給するための配管工事 |
| 冷暖房設備工事 | 冷房・暖房機器の設置や、それに伴う配管・ダクト工事 |
| 厨房設備工事 | 業務用厨房などで使うシンクや調理機器の設置と配管 |
| 衛生設備工事 | 洗面台やトイレなどの衛生設備の設置と配管 |
| 浄化槽工事 | 生活排水を処理するための浄化槽の設置工事 |
| ダクト工事 | 空気の流れをつくるための金属製の管(ダクト)を設置する工事 |
建設業許可が必要な工事とは
税込500万円以上の管工事を請け負う場合には、都道府県または国土交通省からの建設業許可が必須となります。
しかし、建設業許可を取得するには次の要件を満たす必要があります。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
建設業の経営に関する一定の経験を持つ人が、法人の役員や個人事業主として在籍している必要があります。 - 営業所等技術者(専任技術者)がいること
許可を受けたい業種に関する国家資格や、一定年数の実務経験を持つ技術者を営業所ごとに配置する必要があります。 - 誠実性があること
過去に不正行為や重大な法令違反がないなど、請負契約を誠実に履行できると認められることが求められます。 - 財産的基礎または金銭的信用があること
自己資本や現金預金など、一定の財務基準を満たしている必要があります。 - 社会保険に適切に加入していること
健康保険・厚生年金・雇用保険など、法令で定められた社会保険に加入していることが条件です。 - 欠格要件に該当しないこと
過去に建設業法違反で処分を受けた者や、暴力団関係者などは許可を受けられません。
紛らわしい工事の例
管工事業の対象となるのは、水道管の布設、空調ダクトの設置、給湯設備や浄化槽の設置工事など多岐にわたります。
しかし、他の業種に該当する工程を含むものや、管工事に該当するかわかりづらい工事もあります。
次にそのような紛らわしい工事について説明していきましょう。
浄化槽を設置する場合
浄化槽の設置工事は「管工事業」に該当します。
管工事は金属製の管などを用いて水やガスを送る設備の施工が含まれます。
浄化槽の設置には、配管や給排水の接続などが伴うため建設業許可上は「管工事業」として分類されます。
ただし、浄化槽工事をするには、建設業許可とは別に「浄化槽工事業者」としての登録も必要です。
したがって、浄化槽の設置を業として行う場合は、建設業許可と浄化槽工事業者登録が必要です。
ガス機器の交換工事の場合
ガス機器の交換工事が「管工事業」に該当するかどうかは、工事の内容によって判断されます。
単にガスコンロや給湯器などの機器本体を交換するだけで、配管工事を伴わない場合は、原則として管工事には該当しません。
しかし、機器の交換に際してガス配管の接続や延長、改修などをする場合は、管工事に該当する可能性があります。
ガス機器の交換工事を業として行う場合は、建設業法だけでなく、ガス事業法や高圧ガス保安法などの関連法令にも注意が必要です。
エアコンなどの調機の設置だけの場合
一般的に、エアコンの設置には冷媒配管やドレン配管などの施工が伴うため、「管工事業」に分類されるのが基本です。
特に、空調設備の新設や大規模な交換工事では、配管の接続や加工が必要となるため、管工事としての許可が必要になります。
既存の配管をそのまま使用し機器本体の取り替えのみをする作業であれば、建設業法上の「工事」には該当せず、許可は不要とされることもあります。
また、電源工事を伴う場合は「電気工事士」の資格や電気工事業の登録も必要になるため、実際の工事内容に応じて適切な許可や資格を確認することが重要です。
このようにエアコン設置を業として行う場合は、管工事業と電気工事業の両方の許可が必要な場合もあります。
スプリンクラーや火災報知器の設置を伴う場合
スプリンクラーや火災報知器の設置工事は、建設業法上「管工事」ではなく、原則として「消防施設工事」に該当します。
消防施設工事とは、火災警報設備や消火設備、避難設備などを設置・取り付ける工事を指し、スプリンクラー設備や火災報知器はその代表例です。
ただし、スプリンクラーの配管部分のみを施工する場合には、工事内容によっては「管工事」に該当するケースもあります。
工事の範囲が設備全体の設置か、配管部分に限定されるかによって、必要な建設業許可の業種が異なります。
工事内容を正確に把握し、消防施設工事業または管工事業のいずれに該当するかを判断することが重要です。
管工事の注意点
管工事においては他の業種と密接に関係する工事内容が多く、許可を取得する際には難しい判断となることがあります。
管工事業を取得する際には、次の点に注意しながら申請を進めるようにしましょう。
判断が付きにくい場合は、事前に役所に相談に行ったり専門の行政書士に依頼するのもおすすめです。
電気工事との区分がわかりにくい
建設業において、管工事と電気工事はそれぞれ異なる業種として分類されていますが、実際の現場ではその境界が曖昧になることがあります。
特に空調設備やエアコンの設置工事では、冷媒配管やドレン配管は管工事に該当し、電源の配線やコンセントの設置は電気工事に該当します。
このように一つの工事に両方の要素が含まれる場合、どちらの許可が必要か判断が難しくなるのです。
誤った業種で許可を取得していると、建設業法違反となるリスクもあるため、工事内容を正確に把握し、適切な業種で申請することが重要です。
管工事をメインで行う場合、電気工事業と管工事業の両方の許可を有している業者も少なくありません。
下水道や道路配管との関係が難しい
管工事で注意すべき点のひとつが、下水道や道路配管との関係です。
特に公共インフラと接続する工事では、自治体や関係機関との調整が必要であり、工事の範囲や責任分担が曖昧になりやすくなります。
たとえば、建物からの排水を公共下水道に接続する場合、敷地内の配管は管工事業者が担当しますが、道路下の本管との接続部分は自治体の管理下にあるため、許可申請や立会いが必要です。
また、道路の占用や交通規制も行わなくてはならないので、安全対策にも十分な準備が必要となります。
管工事の際に必要な登録がある
管工事の際には、建設業許可だけでなく場合によっては別に登録が必要となる場合があります。
たとえば、水道工事の場合は、各自治体の「指定給水装置工事事業者」としての登録が求められることがあり、登録がなければ工事を請け負えない場合があります。
同様に、下水道接続工事では「排水設備指定工事店」としての登録が必要な場合もあります。
さらに、ガス配管工事の場合には「液化石油ガス設備士」などの資格や、ガス事業者の指定を受ける必要があります。
これらの登録は、地域や工事の種類によって異なるため、事前に施工エリアの自治体や関係機関に確認することが重要です。
管工事業に必要な資格
「管工事業」は、専門性の高い分野であり、この業種で建設業許可を取得するためには、一定の実務経験や国家資格を有する技術者の配置が求められます。
ここでは管工事業に必要な資格の種類や取得方法、実務経験などについて解説していきます。
管工事施工管理技士
管工事施工管理技士は、給排水・空調・ガスなどの配管工事において、施工計画の作成や工程・品質・安全管理をする国家資格です。
資格には1級と2級があり、1級は大規模工事の監理技術者、2級は中小規模工事の主任技術者として認められます。
試験は「第一次検定(学科)」と「第二次検定(実地)」に分かれており、両方に合格することで資格が取得できます。
2024年度以降、1級は19歳以上、2級は17歳以上であれば第一次検定を受験可能となり、実務経験は第二次検定の受験時に必要となります。
一次検定の合格者には「技士補」の称号が与えられ、一定の条件下で現場に配置されることも可能です。
建築設備士
建築設備士は、建築物の空調・給排水・電気設備などの設計に関して、建築士を補助する国家資格です。
管工事においては、給排水や空調設備の設計・監理に関する専門知識を有する技術者として、重要な役割を担います。
受験資格を取得するには、まず所定の学歴や建築関連資格を取得し、さらに建築設備に関する実務経験を積む必要があります。
受験資格を満たした後、一次試験(学科)と二次試験(設計製図)に合格することで資格が付与されます。
設備設計の専門性を高めたい管工事従事者にとって、キャリアアップに直結する資格です。
技術士
技術士(建設部門・上下水道または衛生工学など)は、管工事に関する高度な専門知識と応用力を有する国家資格で、設計・施工・維持管理における技術的責任者としての役割を担います。
特に上下水道や空調・給排水設備の分野で活躍する技術者にとっては、技術士資格は専門性の高い資格です。
取得には、まず技術士一次試験(基礎科目・適性科目・専門科目)に合格し、その後、実務経験(通常4年以上)を経て技術士二次試験(筆記と口頭試験)を受検します。
一次試験は誰でも受験可能ですが、二次試験は実務経験が必須です。
管工事分野での公共工事の設計・監理業務に携わるためには、技術士資格の取得が大きな武器となります。
技能資格
配管技能士は、管工事における技能を証明する国家資格です。
資格は「建築配管作業」と「プラント配管作業」に分かれ、それぞれ1級・2級・3級の等級があります。
試験は学科と実技で構成され、実技では配管の組み立てや溶接、図面の読み取りなどが問われます。
受験資格は等級により異なり、3級は実務経験がなくても受験可能、2級は2年以上、1級は7年以上の実務経験が必要です。
また、職業訓練校や専門学校を修了している場合は、必要な経験年数が短縮されることもあります。
合格し証書が交付されると「技能士」が名乗れるようになり、転職や独立、公共工事の受注などで有利になります。
実務経験のみ
学歴や国家資格がなくても「実務経験」のみで営業所等技術者(専任技術者)になることが可能です。
10年以上の実務経験があれば資格保有者と同等に扱われます。
ただし、単なる作業員としての経験ではなく、施工管理・図面作成・工程管理・品質管理など、技術的な業務に従事していたことが求められます。
また、他の業種での経験はカウントされず、あくまで「管工事」に該当する内容で10年の実務経験が必要です。
実務経験を証明するために、工事契約書・注文書・請書といった書類を必要年数分準備する必要もあります。
10年間の実務経験が連続している必要はありませんが、工事の期間の積算には各自治体によって判断が異なることもありますので注意が必要です。
管工事業に関するよくある質問
工事が管工事に該当するかどうか、また登録が必要かどうか、判断に迷うケースも少なくありません。
管工事業に関するよくある質問を具体的に解説していきましょう。
水道設備の修理だけなら許可は不要?
簡単な設備修理であれば許可が不要な場合もあります。
たとえば水漏れ箇所の簡易な補修であれば許可はいりませんが、配管に手を加えるような作業は許可や資格が必要になります。
また、給水管や排水管、止水栓の交換などの場合は、給水装置工事主任技術者や排水設備工事責任技術者などの資格が必要であり、指定工事店でなければ施工できない場合もあります。
これらは自治体によって基準が異なることもあるため、事前に確認するのが安心です。
給湯器の電気配線の工事も行う場合は?
給湯器の設置にあたっては、給水管・給湯管・ガス管などの接続や延長といった配管作業を含む場合は「管工事」に該当します。
給湯器の電源配線の新設や延長などは「電気工事」に該当し、作業には「電気工事士」の資格に加えて「電気工事業」の登録が求められます。
したがって、配管工事と電気工事の両方を一括で行う場合は、内容に応じてそれぞれの業種に対する許可や登録の取得が必要になります。
蛇口などの器具交換だけなら許可はいらない?
蛇口やシャワーヘッドなどの水まわり器具の交換工事については、一般的に建設業許可は不要とされています。
蛇口の交換やパッキンの取り替えといった作業は、請負金額が税込500万円未満の軽微な工事に該当するためです。
また、これらの作業は「給水装置未満」の範囲とされることが多く、自治体の指定工事業者でなくても対応可能なケースがほとんどです。
器具の単純な交換であれば許可や資格は不要ですが、工事の範囲が広がると許可や登録が必要になることがありますので注意しましょう。