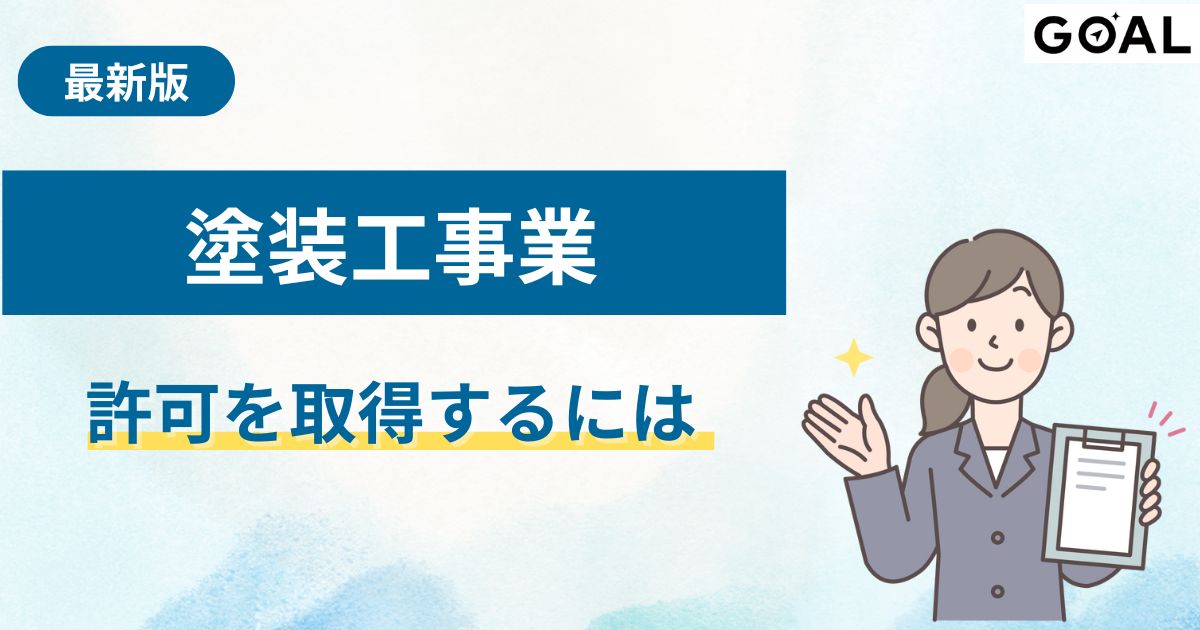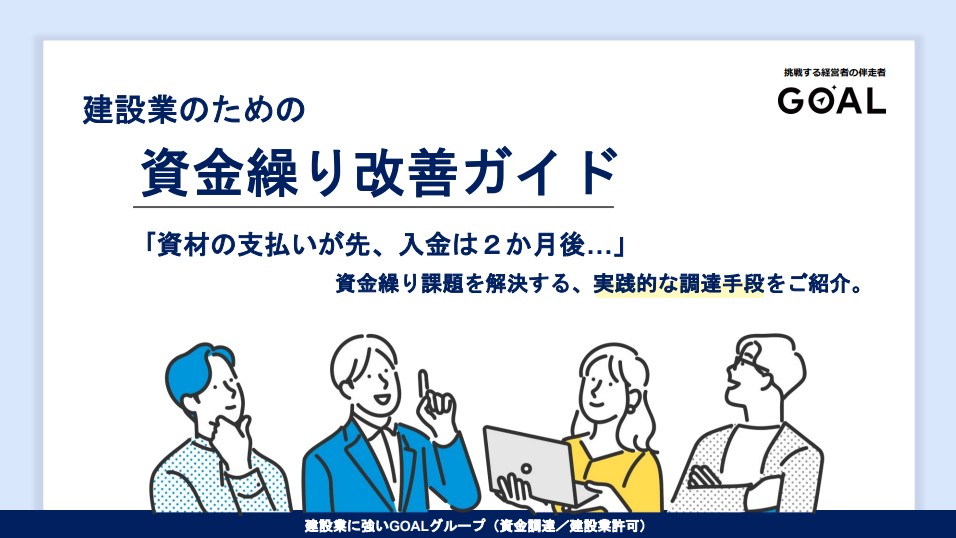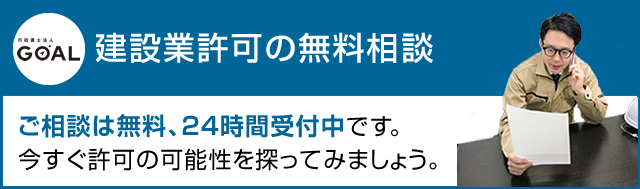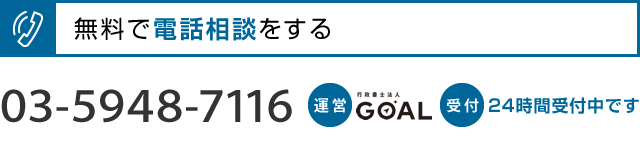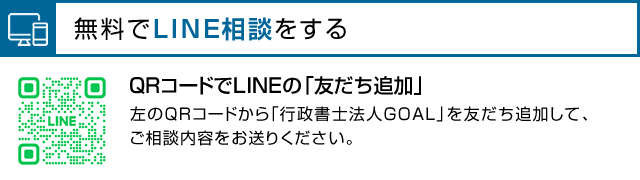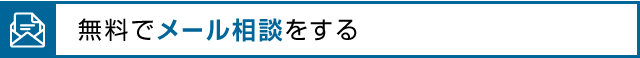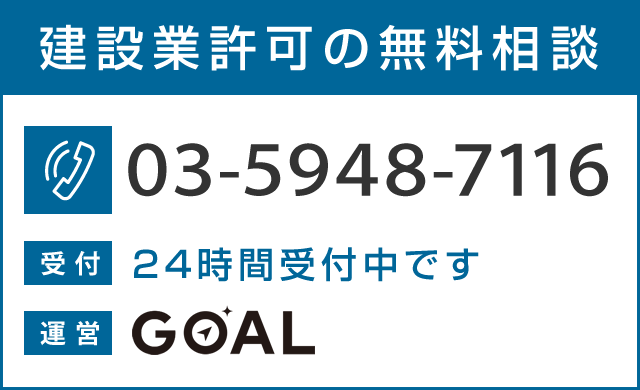塗装工事業を営むうえで、「建設業許可が必要になるタイミングはいつか」「どんな資格や経験が求められるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。
特に塗装工事は他業種との境界が曖昧になりやすく、その違いを正しく理解しておくことが求められます。
この記事では、塗装工事業に関する許可取得の基本から、よくある質問、注意すべき実務上のポイントまでまとめました。
路面標示工事・防水塗装などの判断基準についても触れながら、現場目線でわかりやすく解説していきます。
目次
建設業許可における塗装工事業
建設業許可には29種類の業種があり、そのひとつに「塗装工事業」があります。
この業種は、建物や構造物に塗料や塗材を吹き付けたり、塗り付けたり、貼り付けたりする工事が対象です。
建設業許可を取得することで、大きな金額の塗装工事が請け負えます。
事業の信頼性向上や取引先からの評価にもつながるため、塗装業を営むうえで許可取得は大きな意味を持つといえるでしょう。
塗装工事業の具体例
塗装工事業の業務内容は多岐にわたります。
一般的にイメージされる塗装工事は、外壁や屋根の塗り替えなどです。
そのほかにも鉄骨や橋梁などの防錆処理、床面のライン引き、さらには特殊な塗料を用いた機能性塗装まであります。
次に、建設業許可における「塗装工事業」の具体的な施工例を取り上げながら、どのような工事が該当するのか解説していきましょう。
一般的な塗装工事
塗装工事は、建築物の保護や美観の向上を目的として行われる重要な工事です。
屋根などの建築物のほか、鉄骨・鋼材といった金属部材、さらには木材部分にも塗装が施されます。
建築物への塗装では、紫外線や雨風からの劣化を防ぐため、防水性や耐候性に優れた塗料が選ばれます。
外壁にはシリコン系やフッ素系塗料がよく使われ、耐久性と美観の両方が求められます。
一方、金属部材には防錆効果のある塗料が必要です。
鉄骨や手すりなどは、下地処理としてサビ止め塗装を施したうえで、耐候性の高い塗料で仕上げるのが一般的です。
木材に対しては、木目を活かすクリヤー塗装や、防腐・防虫効果のある保護塗料が使用されます。
屋外のウッドデッキや窓枠などは、定期的な塗り替えによって長持ちします。
素材ごとに適した塗料や施工方法を選ぶことで、建物全体の耐久性と美観が保てます。
溶射工事・ライニング工事
塗装工事業の中でも、専門性の高い分野として「溶射工事」と「ライニング工事」があります。
どちらも素材の保護や機能向上を目的とした施工ですが、工法や対象物には違いがあります。
まず溶射工事は、金属粉末などの溶射材を高温で溶かし、対象物の表面に吹き付けることで、耐摩耗性や耐食性を高める技術です。
橋梁やプラント設備など、過酷な環境下で使用される構造物に多く採用されており、長期的な保護効果があります。
一方、ライニング工事は、既存の配管やタンクの内面に特殊な樹脂や塗料を流し込むことで、腐食や漏水を防ぐ施工方法です。
古い配管を交換せずに再生できるため、工期の短縮やコスト削減につながる点が大きなメリットといえるでしょう。
なお、建設業許可の区分では、これらの工事は原則として「塗装工事業」に該当します。
ただし、施工内容や目的によっては「管工事」や「防水工事」「機械器具設置工事」に分類される場合もあるため、許可申請時には注意が必要です。
布張り仕上工事
布張り仕上げ工事は、建物の壁面に布地を貼り付け、その上から着色を施すことで、布の質感を活かした独特の仕上がりを実現する工事の一種です。
一般的な塗装とは異なり、素材の選定や貼り方によって印象が大きく変わるため、内装のデザイン性を重視する場面で行われる工事です。
使用される布地には、寒冷紗やレース地、ヘッシャンクロスなどがあり、建物の用途や雰囲気に合わせて選ばれます。
貼り方にも種類があり、布地をそのまま突き付けて貼る方法と、一部を重ねて貼る重ね張りなどがあります。
このような布張り仕上工事で、着色を伴う場合は「塗装工事業」に分類されます。
着色がない場合は「内装仕上げ工事」となりますのでよく確認をしましょう。
鋼構造物塗装工事
鋼構造物塗装工事は、橋梁や鉄骨などの金属構造物に対して、防錆や耐候性を目的とした塗装を施す専門的な施工です。
これらの構造物は屋外で長期間使用されるため、雨風や紫外線による劣化を防ぐための塗膜処理が必要です。
たとえば橋梁では、交通量や気象条件にさらされることから、塗料の選定と下地処理が非常に重要です。
高耐久性の塗料を使用し、ブラスト処理などで錆を除去したうえで塗装を行うことで、構造物の寿命を延ばせます。
また、鉄骨部分の塗装も同様に、錆防止や耐久性が向上の点で構造物の安全性にも影響する重要な工程です。
路面標示工事
路面標示工事とは、道路上に白線や矢印、文字などの標示を施すことで、車両や歩行者の安全な通行を促す工事です。
専用の塗料を用いてアスファルトやコンクリートの路面に直接描くため、耐久性や視認性が求められます。
交通量の多い幹線道路や交差点では、夜間でも見やすい反射材入りの塗料が使用されることもあります。
施工方法には、加熱式のペイントマシンによるライン引きや、手作業による文字・記号の描画などがあり、現場の状況に応じて使い分けられます。
特に高速道路や都市部では、施工精度が交通の流れに直結するため、熟練した技術が必要です。
なお、建設業法上では路面標示工事は「塗装工事業」に分類されます。
舗装工事と混同されがちですが、路面の表面を固めるのではなく、標示を描くことが主目的であるため、許可申請時には区分の確認が重要です。
許可が必要な塗装工事とは
塗装工事を事業として行う場合、すべての工事に建設業許可が必要ではありません。
建設業法では、請負金額が「税込500万円以上」の工事を受注する際に、許可の取得が義務付けられています。
たとえば、外壁塗装の見積もりが450万円でも、足場組み立てなどを加えると総額が500万円を超えるケースは少なくありません。
その場合、許可を持たずに契約を結ぶと建設業法違反となる可能性があります。
許可が不要な塗装工事とは
建設業法では「軽微な工事」に該当する場合、許可を取得せずに施工できます。
具体的には、請負金額が税込で500万円未満の専門工事が対象です。
たとえば、一般住宅の外壁塗装や屋根の塗り替えなど、小規模な改修工事はこの範囲に収まるケースが多く、許可なしでも施工可能です。
また、契約を分割して500万円未満に見せかける行為は認められておらず、実質的な総額で判断されます。
そのため、金額の管理だけでなく、契約内容の整合性も重要です。
このように、許可が不要な塗装工事は一定の条件下でのみ認められており、誤った判断は無許可営業とみなされるリスクもあります。
事業の継続性や信頼性を考えるなら、将来的な許可取得も視野に入れておくとよいでしょう。
塗装工事業と他業種との違い
建設業の中には、似たような作業内容を含む業種がいくつもあります。
塗装工事業と聞くと外壁や鉄骨への塗装を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は内装仕上げ工事や防水工事など、近い領域の業種と重なる部分も少なくありません。
とはいえ、それぞれの業種には明確な区分があり、施工の目的や方法によって分類が分かれるのが特徴です。
次に、塗装工事業と他の建設業種との違いについて整理していきましょう。
防水工事
塗装工事業と防水工事は、どちらも建物の保護を目的とした施工です。
防水工事は、雨水や湿気の侵入を防ぐことを目的とした施工で、アスファルトやシーリング材、塗膜材などを用いて屋上やバルコニー、外壁の隙間などに防水層を作るものです。
施工方法には、塗膜防水・シート防水・シーリング工事などがあり、素材や部位に応じて使い分けられます。
一方、塗装工事業は、建築物や構造物に塗料や塗材を吹き付けたり塗り付けたりすることで、外観の美しさや耐候性を高める工事です。
外壁や鉄骨、木部などが主な対象となり、防錆や遮熱などの機能を持つ塗料が使われることもあります。
このように工事の内容や使用する材料において明確な違いがあるのです。
内装仕上工事
建設業の中でも「内装工事」と「塗装工事」は混同されやすい分野です。
まず、内装工事は建物の内部空間を整える工事で、壁紙の貼り替えや床材の施工、天井の仕上げなどが主な対象です。
インテリア性や快適性を高めることが目的で、店舗やオフィスの改装などにも多く用いられます。
一方、塗装工事は建物の外壁や鉄骨、木部などに塗料を塗り付けることで、保護や美観の向上を図る工事です。
耐候性を持たせるために、素材に応じた塗料を選定し、下地処理から仕上げまでを行います。
外部だけでなく内部の塗装も含まれる場合がありますが、あくまで「塗る」ことが主目的となるのです。
塗装工事業の許可取得方法
塗装工事業で建設業許可を取得するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、申請には専門的な知識や書類の準備が求められるため、初めての方にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。
次に塗装工事業の許可取得の方法を解説します。
許可が必要な工事の金額基準
建設業許可が必要かどうかは、工事の内容だけでなく「請負金額」によっても判断されます。
特に専門工事の場合、1件あたりの請負金額が税込で500万円以上になると、建設業法に基づき許可が必要です。
税込500万円未満の工事(軽微な工事)をする場合は許可は不要です。
この金額には、材料費や人件費、消費税などすべての費用が含まれるため、見積もり段階で確認するようにしましょう。
許可取得の要件
建設業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。
まず重要なのが「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」の設置です。
これは、建設業の経営経験が一定期間ある人物を役員などに配置することで、事業の継続性と信頼性を担保するための条件です。
次に「営業所等技術者(専任技術者)」の配置も必要です。
営業所ごとに、資格や実務経験を持つ技術者を常勤で置くことが求められます。
さらに「誠実性の確保」も要件のひとつです。
過去に重大な契約違反や法令違反がないことが前提となり、反社会的勢力との関係がないことも確認されます。
加えて「財産的基礎または金銭的信用」があることも必要です。
一般建設業であれば500万円以上の自己資本や資金調達能力が求められます。
最後に「欠格要件に該当しないこと」が条件となります。
これには、成年被後見人や破産者など、一定の法的制限を受けている者が含まれます。
許可取得の流れ
最初に、自社が取得すべき許可の種類を決めることから始めましょう。
そして、営業所の所在地や数によって「知事許可」か「大臣許可」のどちらかとなります。
また請け負う工事の規模により「一般建設業」か「特定建設業」かを選ぶ必要もあります。
その後、必要書類の収集と作成をしましょう。
登記簿謄本や納税証明書、資格証明など、提出書類は多岐にわたるため、早めの準備が肝心です。
書類が整ったら、管轄の窓口へ申請を行い、手数料を納付します。
申請後は審査期間に入り、通常は1〜2か月程度で許可の可否が通知されます。
許可が下りた後も、建設業許可票の掲示や決算変更届の提出など、継続的な管理が必要になります。
塗装工事業者が注意すべきポイント
塗装工事には準備作業が含まれることが多く、これらも許可対象の工事として扱われる点に留意が必要です。
単なる付帯作業と誤認されがちですが、実際には塗装工程の一部として認識されます。
また、塗装工事は外壁や鉄骨だけでなく、路面標示やライニング、溶射など多様な施工を含む場合があります。
こうした工事が他業種の許可区分に該当する可能性もあるため、業種の選定は慎重に行いましょう。
特に、塗膜防水などは防水工事業との境界が曖昧になりやすく、判断を誤ると申請内容に不備が生じることもあります。
塗装工事業に必要な資格
専任技術者には一定の資格や実務経験が必要です。
資格がある場合は施工管理技士や技能検定の合格者が対象となります。
ただし、資格がない人でも専任技術者になれる場合もあります。
次に塗装工事業に必要な資格の種類を紹介しましょう。
施工管理技士
建設業において代表的な資格が「施工管理技士」です。
特に、建築施工管理技士(仕上げ塗装)や土木施工管理技士(鋼構造物塗装)は、塗装工事に対応できる資格として認められています。
特定建設業であれば一級の資格が求められます。
一般建設業許可の場合は、二級施工管理技士でも要件を満たせます。
技能資格
代表的な技能士資格としては、「建築塗装」「金属塗装」「木工塗装」「噴霧塗装」「路面標示施工」などの技能検定が挙げられます。
これらは1級・2級に分かれており、2級の場合は合格後に3年以上の実務経験が必要です。
また、登録基幹技能者制度における「建築塗装基幹技能者」や「外壁仕上基幹技能者」などの資格も、現場管理能力を備えた人材として評価されます。
これらは、指導監督的な実務経験があることを前提に認定されるため、キャリアのステップアップにも有効です。
実務経験
資格を持っていない場合でも、10年以上の実務経験があれば専任技術者として認められる可能性があります。
国家資格や指定学科の卒業歴がない人にとっては、現場経験が活かせます。
ただし、実務経験は単に「建設業に携わっていた」というだけでは不十分で、申請する業種と一致した工事経験が10年以上必要です。
塗装工事業の許可を申請する場合は塗装工事に従事した期間のみが対象となり、他業種の経験は合算できません。
また、経験の証明には契約書や請求書、通帳の入出金記録など、工事の実績を裏付ける書類が求められます。
勤務先が建設業許可を持っているかどうかによって必要書類の内容も変わるため、事前に確認しましょう。
塗装工事業の許可取得でよくある質問
許可の申請時にはわからないことも多くあります。
疑問を事前に整理しておくことで申請準備がスムーズに進み、手戻りのリスクも減らせます。
特に塗装工事業は、他業種と区分が重なるケースもあるため、工事内容に応じた判断が求められます。
塗装工事業の許可取得に関してよく寄せられる質問を取り上げてみました。
塗装工事業の範囲に下地処理は含まれる?
建設業許可の区分において、下地調整やブラスト工事などの準備作業は塗装工事の一部として含まれます。
たとえば、外壁塗装を行う際には、旧塗膜の除去やひび割れの補修、錆の除去などを事前に行う必要があります。
これらの作業は、塗料の密着性や仕上がりの品質を左右する重要な工程であり、単なる付帯作業ではなく、塗装工事の本質的な一部と考えられています。
また、ブラスト処理のように金属表面を清浄化・粗面化する作業も、塗装の前提条件として位置づけられています。
こうした準備工程を除外してしまうと、工事の実態と申請内容にズレが生じる可能性があるため注意が必要です。
防水塗装は「塗装工事業」か「防水工事業」か?
「防水塗装」は、塗料を使って防水性を持たせる工事を指します。
しかし、建設業許可の区分では「塗装工事業」と「防水工事業」のどちらに該当するか判断が分かれることがあります。
たとえば、塗料を塗ることで防水性を高める「塗膜防水」は、液体状の防水材を使って膜を形成する工法であり、一般的には「防水工事業」に該当することが多いです。
また、同じような工事でも、施工対象が屋上か外壁か、目的が美観か防水かによって判断が分かれることもあるため、申請時には工事内容を具体的に記載することが求められます。
誤った区分で申請すると、許可が下りない可能性があるので事前確認が必要です。
路面標示工事を行うには必ず塗装工事業の許可が必要?
路面標示工事は原則「塗装工事業」に該当します。
ただし、舗装工事と混同される場合もあるため注意が必要です。
舗装は路面そのものを形成・補修する工事であり、標示とは目的も内容も異なります。
また、標示の施工方法によっては、反射材や特殊塗料を用いることもあり、技術的な要件も変わってきます。
このように、路面標示工事を行う際には、工事の内容を踏まえたうえで塗装工事業としての許可が必要かどうかを判断することが大切です。