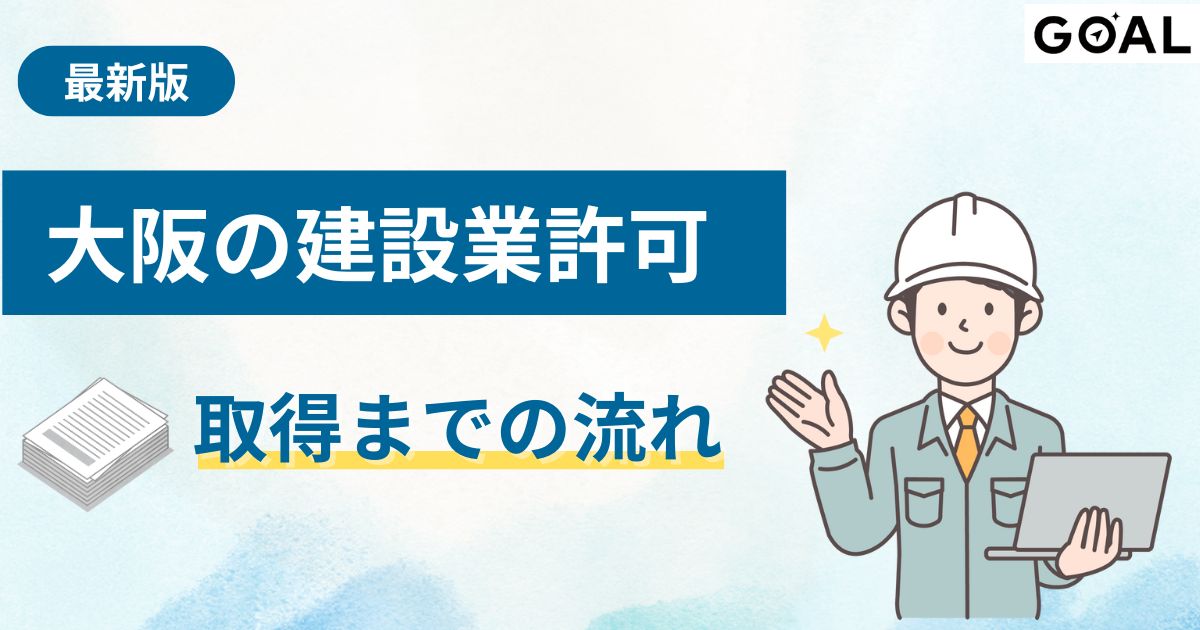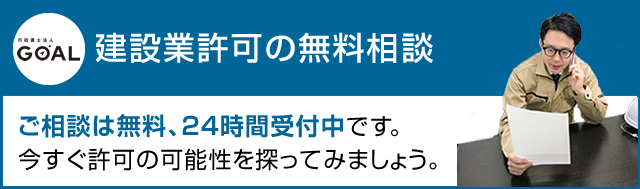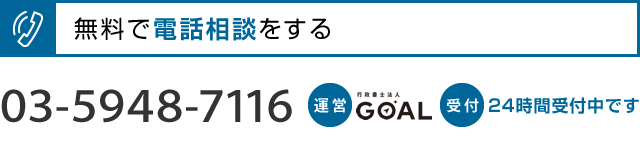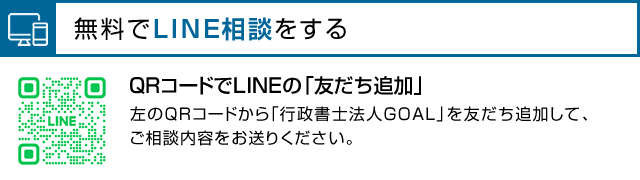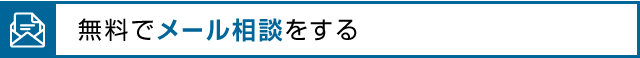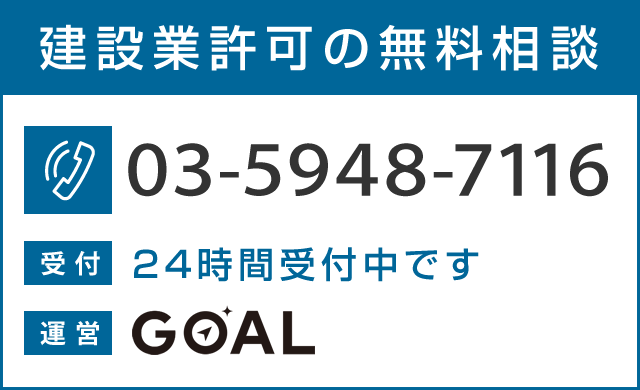関西の建設業界は、大阪・関西万博のパビリオン建設や周辺インフラ整備などにより、盛り上がりを見せていました。
さらに大阪では、大阪IR(統合型リゾート)の計画が認定され、うめきた2期地区の大規模再開発などにより、今後も建設需要が高まっています。
そのため大阪府の建設業者数は2018年を皮切りに急激に上昇しており、東京都に次いで二番目に多い数となっています。
今回は建設業許可の基本から大阪府での申請手続き、注意点やポイントを詳しく解説します。
行政書士法人GOALでは、大阪市中央区淡路町に大阪支店を構えております。府内の建設業者様を中心に建設業許可のサポートを行っています。
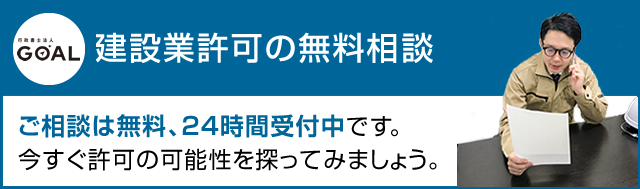
- 上場企業や大手グループへのサポート実績多数!複雑な状況もお任せください
- 簡単なヒアリングで建設業許可の取得可能性の判断をお伝えします
- 許可要件を満たさない場合は、最短取得までの準備方法をご案内いたします
目次
建設業大阪府知事許可の基礎知識
建設業を営む業者は、ある一定の条件を満たす工事に関して建設業許可を取得し業務を行わなければなりません。
建設業許可は、業態によって許可申請を行う都道府県が異なります。
大阪府内で営業し他県には建設業を営む支店や営業所がない事業者は、大阪府知事許可を申請します。
また、許可を取得したら全ての建設工事が行えるというわけではありません。
建設業許可を取得するにはさまざまな要件をクリアする必要もあります。
ここでは、建設業許可の基本と大阪府の建設業界の現状について解説していきましょう。
建設業許可とは
1件500万円(税込)以上の工事(建築一式は1,500万円以上、または延べ面積150㎡超の木造住宅)は、建設業許可を取得する必要があります。
税込500万円未満の軽微な工事には許可不要ですが、許可を取得していることで信頼性が大きく高まることもあり、そのために許可を取得する業者も少なくありません。
建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」があります。
知事許可は1つの都道府県内だけで営業する場合に必要で、大阪府内の営業所で工事契約等を行う業者は「大阪府知事許可」を申請します。
さらに建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。
発注者から直接請け負う一件の元請工事について、下請に出す金額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円未満)の場合は「特定建設業」を取る必要があります。
それ以外の工事を行う場合は「一般建設業」となり、中小企業や個人事業主が申請する場合、多くは一般建設業となります。
許可の有効期間は5年間で、期限が来る前に更新申請をしなければなりません。
また、許可要件に関わる変更事項があった場合はその都度変更届を決められた期日までに提出する必要があります。
大阪府の建設業界の特徴
2024年の建設業の倒産件数は、全国で1,924件と過去10年間で最多を記録しました。
特に大阪府では255件と都道府県別で最多となっており、資材価格の高騰や労務規制が影響していると思われます。
なかでも従業員数5人未満の小規模事業者が倒産の約8割を占めており、担い手不足や経営不振などがその大きな理由です。
そして大阪府知事の許可業者数は26,578社で東京都に次いで全国第二位です。
大阪はかつてオリンピックの誘致ができず様々なインフラ工事が中断していましたが、大阪・関西万博の影響で再び工事が始まり、これを機に大阪の建設業界は活性化しました。
このように建設業者数が急激に増えている一方で、倒産数も増えてきているというのが今の大阪の建設業界の実状です。
この対策として、大阪府では「建設工事従事者の安全および健康の確保に関する大阪府計画」が策定され、作業員の健康を守り、持続可能な労働環境への取り組みが行われています。
猛暑日を作業不能日としたり、女性の労働者の確保にむけた制度の整備や、施工体制の点検やICT活用による施工体制の見える化など、府を挙げてのさらなる建設業界の活性化を目指しています。
建設業許可取得の条件
建設業許可を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
- 営業所技術者等(専任技術者)
- 財産的基礎要件
- 誠実性
- 欠格要件
- 社会保険の加入
この条件は大阪だけにあるものではなく、全国どこで建設業許可を取得しても同じ条件となっています。
人的要件や時間的要件などがあり、許可が必要になってから準備をしたら工事に間に合わない場合もあります。
前もって条件を確認し、場合によっては先に許可取得を検討するのもよいでしょう。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)
建設業許可の「常勤役員等」とは、過去に建設業の経営に携わった実績がある役員または事業主のことです。
常勤役員等は「経営業務の管理責任者(経管)」とも呼ばれています。
建設業の経営に必要な経験年数は原則5年以上で、法人・個人事業主問わず同じ条件となっています。
ただし、法人役員としての経験や補佐的な立場での経験も一部考慮される場合があります。
建設業許可を取得する業者は必ずこの「常勤役員等」を置かなくてはなりません。
もし自社に該当する人がいない場合は、他社から要件を満たす人を役員として就任させたり、自社の役員が5年以上の建設業の経験を積むまで待つ必要が出てきます。
営業所技術者等(専任技術者)
建設業許可を取得するには、業種に応じた国家資格や一定年数の実務経験を持った「営業所技術者等」を配置する必要があります。
営業所技術者等は「専任技術者」とも呼ばれ、建設業を行う営業所にそれぞれ置かなくてはなりません。
この資格は施工管理技士、建築士、電気工事士などがあり、取得したい建設業の業種により異なります。
国家資格を持たない場合は、必要とする業種の実務経験を10年以上積んだ人や、指定された学科を卒業し所定の年数の実務経験を積んだ人でも営業所技術者等になれます。
実務経験の場合、業種が異なる時はその証明期間を重複してカウントすることはできません。
また、営業所技術者等はその営業所に常勤でなくてはなりません。
派遣労働者や日雇いなどの技術者は、営業所技術者等になれませんので注意が必要です。
さらに、一人の技術者が複数の営業所の営業所技術者等になることもできません。
財産的基礎要件
建設業許可を取得するためには、自社の資金調達力を証明する必要があります。
具体的には次のものになります。
- 自己資本500万円以上
- 直近の決算で500万円以上の現金預金を保有していること
- 許可申請の直前5年の間に許可をうけていたこと
創業間もない企業でも、預金残高証明書や融資実行通知書などで資金力を証明することで、許可取得が可能です。
特定建設業の場合は、直前決算においてさらに下記の条件が必要となります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上あること
- 自己資本の額が4,000万円以上あること
上記のうち、資本金額については申請日までに増資をしその登記を済ませておくことで、直前決算に条件を満たしていなくても認められます。
誠実性
誠実性とは次のようなことをいいます。
「法人である場合においては、当該法人またはその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者または支配人が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと」
不正な行為とは、建設工事に関して法律に反するような行為を言います。
具体的には、労働者の安全衛生管理に関する違反や詐欺・脅迫行為などのことです。
また不誠実な行為とは、虚偽の報告や手抜き工事をしたり、工事代金の支払いを期限内に行わないなどです。
建設工事は請負契約で完工するまでに長期間かかるものもあり、発注者と受注者との間に信頼関係が求められます。
元請業者にとっては工事の完成や品質の保証が大事であり、下請業者にとっては現場の安全性や支払いがしっかりとされるかどうかも重要です。
これらの理由により、建設業許可を取得する業者には誠実性が求められるのです。
欠格要件
建設業許可を取得したい会社の役員または個人事業主は、欠格要件にあてはまってはいけません。
主な欠格要件は次のようなものになります。
- 法人の役員・個人事業主等が、破産者ではないこと
- 法人の役員・個人事業主等が、禁固以上の刑に処せられていないこともしくは刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していないこと
- 営業の停止もしくは許可の取り消しを受けてから5年を経過していないこと
- 暴力団員ではないことまたは暴力団員等によって事業活動が支配されていないこと
禁固刑の場合は、状況を問わず5年間は建設業許可を取ることはできません。
また、許可取り消しなどの処分を受けている場合、会社名を変えてすぐに許可を取り直そうとする場合も考えられますので、5年間の禁止期間が設けられています。
暴力団の関係者や経営に暴力団が関わっている場合も、欠格要件に該当し許可取得はできません。
社会保険の加入
許可の申請をする業者は、申請日の時点で健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の「社会保険等」に加入していなければなりません。
令和2年10月1日より追加された許可要件であり、建築業においては事故のリスクが高く、人材不足による若手人材の確保や離職防止が導入の背景となっています。
全国土木建築国民健康保険組合に加入していたり、雇用保険適用の労働者がいない場合など、適用除外であると認められる場合もあります。
また、個人事業主の場合は従業員数が5人未満であれば、適用除外となります。
一人親方の場合も社会保険に加入しなければなりませんが、労災保険や雇用保険の加入はその事業形態や労働者を雇っているかどうかで加入できない場合もあります。
大阪府での建設業許可申請手続き
大阪で建設業許可を取得する場合、大阪府住宅建築局建築指導室建築振興課で申請をします。
申請書類は全国ほぼ同一のものとなりますが、都道府県によって独自の書式にて提出する書類や細かい作成指示がでることもあります。
建設業許可の手引きがホームページに公開されていますので、よく読んで申請手続きを進めましょう。
必要書類一覧
大阪府での申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
「表紙1」にまとめるもの
- 許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 大阪府手数料納付要連絡票
- 営業所技術者等一覧表
- 工事経歴書
- 直近3年の事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 健康保険等の加入状況
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 財務諸表
- 定款
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 主要取引先金融機関
「表紙2」にまとめるもの
- 常勤役員等の証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 社会保険等の加入証明書類の写し
- 営業所技術者等証明書
- 資格者証の写し等
- 実務経験証明書
- 許可申請者の調書
- 令3条に定める使用人の調書
- 株主調書
- 商業登記簿謄本
- 事業税納税証明書
- 営業所概要書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 財務諸表
- 決算書または預金残高証明書
申請書類は、閲覧書類の「表紙1」と非閲覧書類の「表紙2」に分けて綴じます。
提出用と申請者の控用に各2冊ずつ作成しますので計4冊を窓口に出す必要があります。
書類はホチキス留めをせずにクリップ等でまとめるようにしてください。
申請の流れ
大阪府で建設業許可を申請する場合は次のような流れとなります。
- 事前相談
- 必要書類の準備
- 書類提出
- 審査
- 許可通知書の受領
初めて申請をする方は、まずは事前相談を受けて内容を把握しておきましょう。
書類の作成及び準備にはかなりの手間と時間がかかります。
書類の提出は事前チェックサービスを受けるか、直接窓口にて審査を受けるかのどちらかとなります。
事前チェックサービスでは時間がかかりますので、急ぐ方は窓口にて対面審査にしたほうがよいでしょう。
書類の不備や不足がなく受付が完了すると、府での審査が始まります。
処理の期間内で書類に不備が見つかった場合は連絡が来ますので、早めに対応をしましょう。
審査が終わると許可通知書が発行されます。
許可の通知書は、営業所の確認のため申請者の営業所あてに転送不要の普通郵便で送られてきます。
営業所の実態が確認できず許可通知書が府に戻された場合は、許可がとり下げられることもありますので注意が必要です。
申請手数料
建設業の申請区分によって申請手数料が異なります。
新規申請の場合、一般建設業もしくは特定建設業のどちらかであれば9万円です。
一般、特定のどちらも申請する場合は18万円になります。
万が一、許可が下りなかったり取り下げをした場合はこの費用は還付されません。
納付場所は咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階の手数料納付窓口で、月~金の9時30分~17時となります。
手数料を納付する際には、申請区分に合わせた大阪府手数料(POS)納付用連絡票を申請者側が準備します。
この納付用連絡票には申請の種類ごとにPOSレジのバーコードの記載があり、納付窓口にてバーコードを読み取り現金にて支払う仕組みになっています。
申請時の注意点
申請書式は大阪府のホームページからダウンロードが可能です。
手引きの記載例に従って作成するとよいでしょう。
記載時に訂正があった場合は、修正テープを使用せずに二重線で消して修正をしてください。
書類には更新用と新規申請用があるものや、別紙もあります。
また、個人と法人とでは準備する書類が異なりますのでよく確認して作成するようにしましょう。
許可の申請先
建設業を営業している事務所と登記簿上の所在地が違う場合、建設業を行う営業所の所在地が大阪府内にあれば大阪府への申請となります。
例えば、本社は東京にあり、大阪営業所だけで建設業の業務を行う場合は大阪府知事許可となります。
さらに他県にも建設業を行う営業所がある場合は、大阪府知事許可ではなく大臣許可となり、申請先は近畿地方整備局となります。
大臣申請の場合は申請方法や書類が異なりますので、確認をしておきましょう。
商業登記簿謄本・戸籍
法人の場合、許可の申請時には定款や商業登記簿謄本の目的欄に建設業を行う旨の記載が必要です。
記載がまだの場合は、申請までに定款を変更し目的変更登記を行っておきましょう。
役員の確認書類については、登記簿謄本に記載のある役員について提出します。
執行役員や監査役については確認書類は不要になります。
また、法人名は登記簿謄本に記載の通り、個人名は戸籍にある文字にて申請します。
処理期間
大阪府では、申請から許可まで通常の処理期間は約30日ほどになります。
この期間は土日、祝日を含みますが、年末年始や大型連休は含みません。
なお、書類の不備がある場合や審査の進捗状況によっては30日を超えることもあります。
許可取得を急ぐ人は、申請する時期に注意しましょう。
大阪府知事許可の独自ポイント
大阪府では手続きの簡素化やIT化に積極的で、独自の対応がされています。
具体的には電子申請を導入したり、事前チェックサービスの利用を進めるなどで効率的な申請の方法がとられています。
では詳しく見ていきましょう。
事前相談や事前チェックサービスの活用
大阪府では申請者に対して事前に相談やチェックサービスが行われています。
これは大阪では申請者の数が多く、建築振興課の窓口の対面審査のみで対応すると混雑したり時間を要してしまうための対策です。
申請者側もこのサービスを利用することで、申請が楽になりますので積極的に利用するとよいでしょう。
事前相談
事前相談には対面と電話があり、大阪府に委託された民間業者が対応をしてくれます。
対面は咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1 階の建築振興課内の相談コーナーで行っており、平日の9時30分から17時まで相談可能です。
電話相談は専用のダイヤルがあり、平日の9時から18時までとなっています。
相談内容は、申請書の記載の方法や準備などについてです。
事前チェックサービス
申請書類の作成ができたら、書類の事前チェックサービスを利用しましょう。
郵送もしくは専用のボックスに投函、または相談コーナーに持ち込みをすると本受付の前に申請書類の内容確認をしてくれるサービスです。
この際に提出する書類は「申請書類一式」「確認書類の写し」「事前チェック送付表」「切手を貼付した返送用大封筒」などです。
郵送する場合は書留で送り、投函する場合には封筒に入れしっかりと口を閉じるようにしましょう。
事前チェックサービスといっても実質的には申請と同じであり、提出する際には必要なものを全てそろえ押印等も済ませて、申請できる状態にまで仕上げておく必要があります。
事前チェックでは主に形式のチェックや要件の確認が行なわれ、受付できる状態にあると判断されれば「事前チェック完了通知書」か送付されます。
ただし不備があると事前チェックができず、書類が揃うまで処理が止まってしまいます。
事前チェックサービスの処理期間は通常で10日ほどかかりますが、受付時の待ち時間や申請窓口対応時間の短縮・来庁の回数が減るなどのメリットもあります。
サポートしてくれる団体を利用する
大阪府には許可取得に関する無料相談会やセミナーを定期的に開催する団体やサポートをする企業などがあります。
個別のアドバイスを受けることも可能で、特に初めての申請者はこういったサポートを受けるのがよいでしょう。
また、建設業許可を専門とする行政書士を利用するのもよいでしょう。
費用は掛かりますが申請の手間や不備が減りますので、忙しい業者や確実に許可を取得したい業者にはおすすめです。
申請時には本人確認が必要
なりすましの申請を防止するため、申請書類には申請者本人ではなく提出する人の氏名や連絡先を記載する箇所があります。
申請・届出の提出や通知書を受領する際には、この提出者本人の確認が必要になっています。
本人確認資料は「運転免許証」「外国人登録証明書・在留カード等」「マイナンバーカード」「(申請者の役員や従業員の場合)社員証等」となり、これらは原本でなくてはなりません。
また、代理人が受け取る際には押印のある委任状の原本が必要です。
本人の確認書類や委任状の提出ができない場合は受付してくれないこともあります。
電子申請
大阪府では、2025年3月時点で電子申請(JCIP)に対応していません。
いつから対応可能になるかはまだ公表されていませんが、大阪府と福岡県以外の行政庁ではすべて電子対応が可能になっていますので、近いうちに大阪府でもできるようになると思われます。
よって現時点での大阪府知事許可の申請方法は、対面での直接審査、もしくは郵送・投函ボックスを利用した事前チェックサービスのみとなっています。
実際の申請者の口コミ
- 「府庁の担当者が丁寧に説明してくれて助かった」
- 「サポートを使ったら一発で通った。無料相談はありがたい」
- 「書類に不備があっても、府庁の職員が親切に教えてくれた」
- 「電話対応がフレンドリーで安心できた」
建設業許可の申請が初めての人にとって、審査を受けるのは不安なことでしょう。
大阪府の建築振興課は親切な対応をしてくれると言った口コミが多く、安心して書類を提出できます。
まとめ
- 自社がどの許可区分に該当するか(知事許可か大臣許可か)を確認
- 常勤役員等(経営業務管理責任者)・営業所技術者等(専任技術者)を事前に確保
- 資金力、誠実性、欠格要件、社会保険加入状況を必ず確認
- 大阪府独自の提出様式や指示に注意して書類を作成
- 事前相談を受け、スケジュールには余裕を持つ
- 審査期間中も連絡が取れる体制を整える
- 許可後は5年ごとの更新手続きも忘れずに行う
建設業許可を取得するためには、人的要件・技術要件・財産要件などさまざまなハードルをクリアしなければなりません。
大阪府での建設業許可申請は、全国共通のルールを基本としつつも、大阪府独自の提出書式や注意点があります。
申請に必要な書類も複雑であり、初めて申請する場合は行政書士などの専門家に相談することもよいでしょう。
しかし、建設業許可取得はポイントを押さえれば決して難しくありません。
そして許可が取得できた後も継続して経営管理や労務管理に十分気を付けましょう。