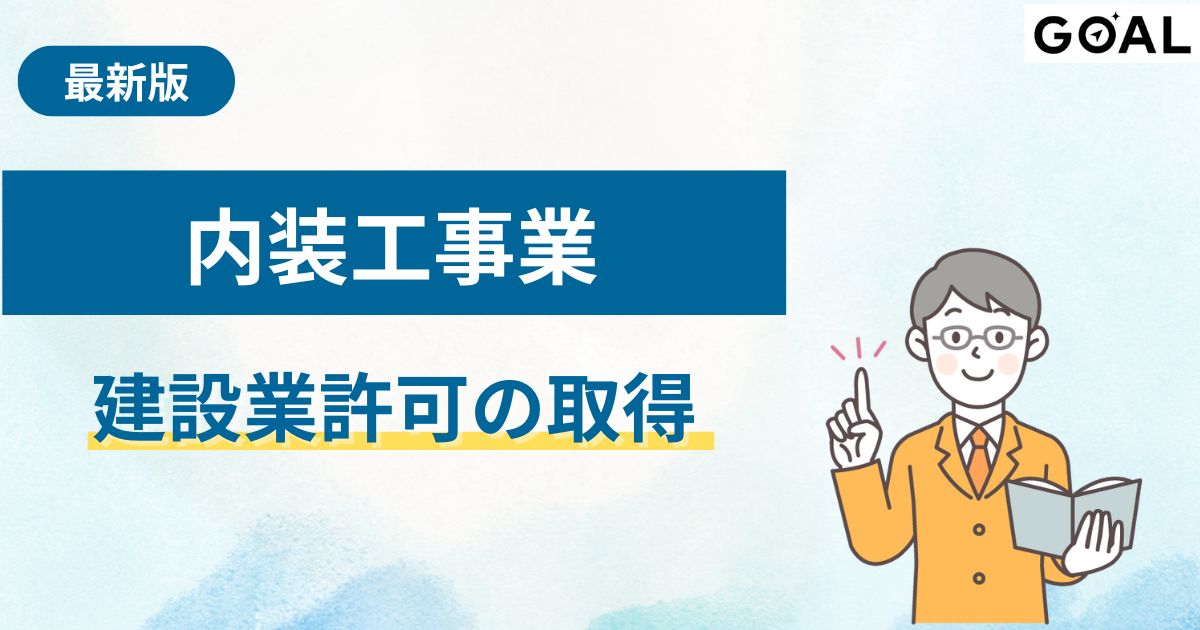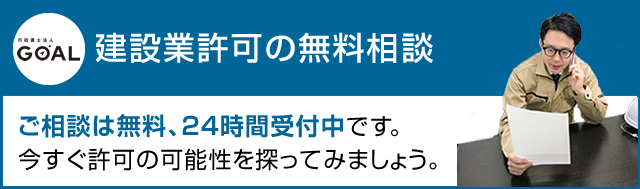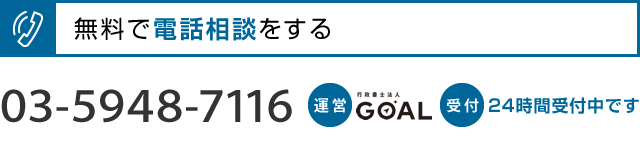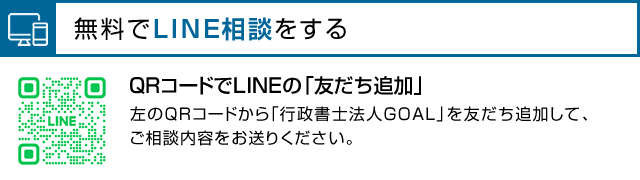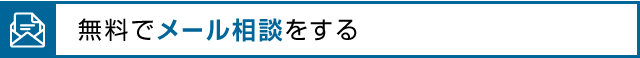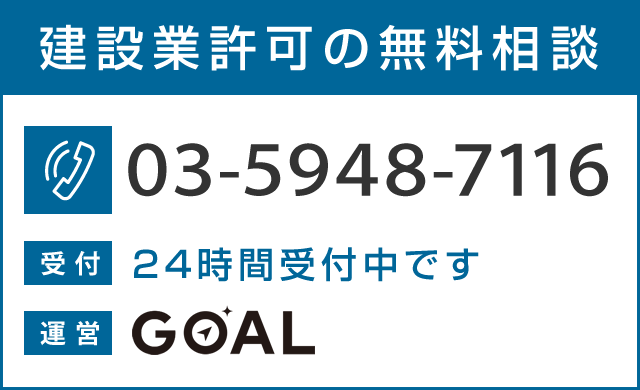内装工事は、住宅・オフィス・店舗など多様な現場で求められる必要性の高い工事です。
請け負う金額や内容によっては建設業許可が必要となるため、正しい知識が欠かせません。
今回は内装工事業の定義や、許可が必要な工事・不要な工事、他業種との違い、必要資格、よくある質問までを解説していきます。
目次
建設業許可における内装工事業
内装工事業は、建設業法に定められた専門工事のうちの一つです。
内装工事とは、天井や壁の仕上げ、床材の張り替えなど、建物の内部を装飾・機能化する工事を指します。
これらの内装工事を建設業許可の上で行う場合、「内装仕上工事業」として許可を取る必要があります。
これは、軽天工事やボード貼りなどの構造的な施工も含まれています。
税込500万円以上の規模の大きい内装工事を施工する場合、許可が必要です。
建設業許可の取得には、ある一定の要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たしていない場合、できる内装工事の範囲は限定されてしまいますので注意が必要です。
主な内装工事の具体例
壁紙の貼り替えや床の張替えなど、建物内部の空間を整える工事が内装工事業に該当します。
内装工事には、以下のような工事が具体的に挙げられます。
- クロス(壁紙)貼り
- フローリング・カーペット・タイル等の床仕上げ
- 天井・壁のボード張り
- 間仕切り(パーティション)の設置
- 一部造作家具の設置
- 店舗や事務所のレイアウト変更工事
このように内装工事の内容は多岐にわたります。
一般的に、内装工事においては次のような流れで作業が行われます。
まず、「軽量鉄骨下地工事」をします。
これは壁や天井の骨組みをつくる工程で、空間の形状を決定づける重要な作業です。
次に「ボード貼り工事」があり、石膏ボードなどを使って壁面を仕上げていきます。
さらに「床仕上げ工事」では、フローリングやタイルカーペットなどを敷設し、使用目的に応じた床材を選定します。
加えて「クロス貼り工事」も一般的で、壁紙を貼ることで空間の印象を大きく左右します。
そのほか「家具工事」など、造作家具を据え付ける工事なども行います。
このように、内装工事はそれぞれの工程が連携しながら空間を形づくっていくため、全体の流れを理解しておくことが大切です。
許可が必要な工事とは
1件あたりの工事請負金額が500万円(税込)以上の場合、内装仕上工事業の建設業許可が必要です。
よって内装工事のすべてに建設業許可が求められるわけではありません。
オフィスの全面改修や商業施設の大規模な内装変更など、比較的規模の大きい案件が該当します。
また、金額に関係なく、元請けや発注者からの信頼を得る目的で許可を取得する事業者も少なくありません。
許可の有無が業者の選定基準になることもあるため、将来的な事業展開を見据えて取得を検討する価値は十分にあるでしょう。
許可が不要な工事とは
次のような工事は、建設業許可がなくても請け負えます。
- 壁紙や床材の貼り替えなど軽微な内装作業(500万円未満)
- 家具の設置、装飾のみを伴う工事
- デザイン監修やプランニング業務のみ
また、追加工事が発生して総額が500万円を超える場合は注意が必要です。
契約時点では不要だった許可が、途中から必要になるケースもあるため、事前の見積もりや契約内容の確認はしっかりと行いましょう。
内装工事と他業種の違い
内装工事は、建物の内部空間を美しく整えることを目的とした仕上げ作業が中心です。
仕上げ作業をする業種は他にもたくさんあります。
たとえば建具工事はドアや窓などの既製品を取り付ける専門分野であり、内装工事とは施工対象や目的が異なります。
さらに、左官工事は壁や床にモルタルや漆喰を塗る作業で、素材や技術も独自のものです。
このように、内装工事は「仕上げ」に特化した業種であり、他業種とは役割や施工範囲が明確に分かれています。
許可申請時には、工事内容の分類を誤らないよう注意が必要です。
次に特に内装工事と混同されがちな他業種との違いを整理しておきましょう。
解体工事
解体工事と内装工事は、どちらも建物に手を加える作業ですが、その目的や範囲には大きな違いがあります。
まず、解体工事は建物そのものを取り壊す作業を指し、構造体や基礎部分まで撤去するケースが一般的です。
老朽化した建物の撤去や土地の再利用を目的とするため、重機を使った大規模な作業になる場合もあります。
一方、内装工事は建物の内部空間を整えるための仕上げ作業です。
壁紙の貼り替えや床材の施工、間仕切りの設置などが主な内容で、建物の構造には触れません。
つまり、解体工事が「壊す」ことを目的とするのに対し、内装工事は「整える」ことに重きを置いています。
また、内装工事の中には「内装解体」と呼ばれる工程もあり、これは既存の内装を撤去して新たな空間づくりをするための基礎となります。
ただし、これは建物全体の解体とは異なり、構造体は残したまま行われます。
大工工事
大工工事と内装工事は、建物づくりに欠かせない工程ですが、それぞれ役割が異なります。
大工工事は、柱や梁、床、屋根などの骨組みを組み立てる「構造的な工事」が中心です。
建物の強度や安全性に直結するため、施工には高度な技術と経験が求められます。
一方、内装工事は、完成した構造体の内部を仕上げる作業です。
壁紙の貼り替えや床材の施工、天井の装飾など、居住性やデザイン性を高めることが目的となります。
つまり、大工工事が「建物を形づくる」工程であるのに対し、内装工事は「空間を整える」工程といえるでしょう。
また、施工時期にも違いがあります。大工工事は建築の初期段階で行われ、内装工事はその後に続く仕上げ工程です。
両者は連携しながら進められますが、専門性が異なるため、担当する職人も分かれています。
管工事と電気工事などの設備工事
設備工事と内装工事は、どちらも建物の快適性を高めるために欠かせない作業ですが、目的や施工範囲には明確な違いがあります。
設備工事は、電気・水道・空調・ガスなど、建物に「機能」を持たせるための工事です。
たとえば、照明の配線やエアコンの設置、給排水管の施工などが該当します。
これらは専門資格が必要な分野も多く、安全性や法令遵守が重視されます。
一方、内装工事は空間の「見た目」や「使い勝手」を整える仕上げ作業です。
壁紙の貼り替えや床材の施工、間仕切りの設置などが代表的で、居住性やデザイン性を高めることが主な目的となります。
両者は現場で連携することも多く、洗面台の設置や照明器具の取り付けなど、設備と仕上げが混在するケースもあります。
リフォーム工事
リフォームは工事全体の総称です。
リフォーム工事と内装工事業は、どちらも建物の快適性や機能性を高める目的がありますが、施工範囲や業務内容に違いがあります。
内装工事業は、壁紙・床材・天井などの仕上げ作業を中心とした専門業種であり、新築や改修時の空間づくりに関与します。
軽鉄工事やボード貼り、クロス施工などが主な業務で、建物の骨格が整った後の「空間の仕上げ」を担います。
一方、リフォーム工事は既存の建物に対して行う改修作業で、内装工事に加えて設備更新や間取り変更、水回りの改修など、より広範な工事を含みます。
住環境の改善やライフスタイルの変化に対応するため、設計から施工までを一括で請け負うケースも多く、総合的な提案力が求められます。
つまり、内装工事業は「仕上げの専門職」、リフォーム工事は「空間全体の再設計」と捉えると、両者の役割が明確になります。
また、リフォーム工事を一括請負する場合は、内装仕上工事業以外の許可も必要になることがあります。
内装工事業許可の取得に必要な要件
内装工事業を本格的に営むには、建設業法に基づく「内装仕上工事業」の許可取得が必要です。
特に、1件あたり税込500万円以上の工事を行う場合や、元請として公共工事や法人案件に関わる際には、許可の有無が信頼性や契約条件に直結します。
許可取得には複数の要件を満たす必要がありますが、事前にポイントを押さえて準備すれば、スムーズに申請ができるでしょう。
ここでは、内装工事業許可の取得に必要な要件について解説していきます。
常勤役員等の要件(経営業務の管理責任者)
常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは、建設業許可を取得する際に必要な要件の一つで、会社の経営を実質的に統括する人物を指します。
法人の場合は常勤役員、個人事業主であれば本人が該当します。
許可を受けようとする建設業に関して、原則として5年以上の経営経験が求められます。
また、契約管理・資金調達・労務管理など幅広い業務を適切に遂行できる能力が必要です。
営業所等技術者の資格・実務経験(専任技術者)
専任技術者とは、建設業許可を取得する際に営業所ごとに配置が義務づけられる技術的責任者です。
許可を受けたい業種に関して、一定の国家資格を有するか、指定学科の卒業+実務経験、または10年以上の実務経験が必要です。
営業所に常勤し、契約内容の確認や技術的な管理を担うため、現場への兼務は一定の条件を除き原則不可となっています。
財産的基礎
「財産的基礎」とは、事業を安定的に継続できるだけの資金力を有しているかを示す要件です。
具体的には、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。
これは、工事の受注後に資材購入や人件費などの初期費用を賄える体力があるかを判断する基準であり、経営の信頼性を裏付ける重要な指標にもなっています。
欠格要件と誠実性
「欠格要件」とは、一定の法令違反歴や社会的信用に関わる事由がある場合、許可を受けられないとする基準です。
たとえば、禁錮以上の刑や建設業法違反による処分歴が5年以内にある場合などが該当します。
一方「誠実性」とは、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないことを指します。
過去の免許取消や営業停止処分歴があると、許可取得が認められない場合があります。
営業所の要件
営業所要件とは、建設業許可申請において「営業所」と認められるために必要な条件です。
契約締結をする事務所であることが前提で、電話・机・台帳などの設備が整い、他社や住居部分と明確に区分されている必要があります。
また、使用権限(自己所有または賃貸契約)があること、看板や表札で外部から営業所と認識できることも重要です。
社会保険の加入は許可要件なのか
建設業許可を取得するうえで、法令上、社会保険への加入は直接的な許可要件には含まれていません。
しかし、実際の審査では社会保険の加入状況を確認され、未加入の場合は是正を求められることが多く、改善されないと許可がおりません。
特に法人は法律上、健康保険や厚生年金への加入義務があるため、未加入のままでは指導対象となります。
また、国や自治体が行う公共工事の入札では、社会保険未加入の企業は原則として参加できません。
そのため、建設業許可の取得や入札へ参加するには、社会保険へ適切に加入しておくことが実質的に必須となります。
内装工事業をするために必要な資格
内装工事業を営むにあたって、必ずしも資格が必要というわけではありません。
ただし、一定規模以上の工事を請け負う場合や建設業許可を取得する際には、技術者として認定される資格が求められます。
たとえば「建築施工管理技士」や「建築士」は、専任技術者として認定される代表的な国家資格です。
また、実務経験が10年以上あれば資格がなくても申請可能なケースもあります。
さらに、インテリアコーディネーターや内装仕上げ施工技能士など、業務の質を高めるうえで有利な資格も存在します。
施工管理技士
内装工事業において施工管理技士は、現場の品質・工程・安全・原価などを総合的に管理する重要な役割を担います。
特に「建築施工管理技士」は国家資格であり、1級と2級に分かれ、担当できる工事規模が異なります。
1級取得者は監理技術者として大規模工事に従事ができ、2級は主任技術者として中小規模の現場を担当可能です。
資格取得により、建設業許可申請時の専任技術者として認定されるほか、転職や昇進にも有利に働きます。
内装工事の専門性を高め、信頼性のある施工体制を築くためにも、施工管理技士の資格はとても重要です。
建築士
内装工事に関わる建築士は、ただオシャレなデザインを考えるだけでなく、安全で使いやすい空間をつくるための設計やチェックも行います。
建築士には「一級」「二級」「木造」の3種類があり、扱える建物の大きさや種類が違います。
たとえば、一級建築士なら大きなビルや商業施設の内装も担当できます。
内装工事では資格がなくても設計はできますが、建築士が関わることで法律に合った安心できる設計となり、トラブルが防げます。
特に店舗やオフィスなどの工事では、建築士のサポートがあると信頼度もアップします。
技能資格
内装工事に関する技能資格の代表が「内装仕上げ施工技能士」です。
これは壁・床・天井などの仕上げ作業に必要な技術を証明する国家資格で、1級・2級・3級に分かれています。
仕上げ内容に応じて「鋼製下地工事」「ボード仕上げ工事」「床仕上げ工事」などの区分があり、実技と学科の両方に合格することで取得できます。
資格がなくても施工は可能ですが、技能士として認定されることで技術力の証明となり、顧客からの信頼や就職・独立時の評価向上につながります。
特に1級取得者は専任技術者として建設業許可申請にも活用でき、キャリアアップにも有利です。
実務経験のみ
請負金額が税込500万円未満であれば、資格がなくても施工可能です。
ただし、建設業許可を取得して事業を拡大したい場合には、一定の条件を満たす必要があります。
資格がない場合でも、内装仕上工事に関する実務経験が10年以上あれば、専任技術者として認定される可能性があります。
この経験は、他業種との合算では認められず、内装仕上工事に特化した実績が求められます。
証明には契約書や請求書、入金記録などの書類が必要です。
無資格でも経験を積み重ねることで、許可取得や信頼性の向上につながる道が開けます。
内装工事業に関するよくある質問
最後に、内装工事業に関するよくある質問をご紹介します。
内装専門で元請けになれる?
内装工事だけを専門にしていても、元請けとして仕事を受けることはできます。
たとえば、店舗やオフィスの改装では、内装会社が設計から施工までを一括して担当するケースもあります。
元請けになると、職人さんの手配やスケジュール管理、品質のチェックなど、責任も大きくなります。
でも、信頼される対応や提案力があれば、内装専門でも元請けとして活躍するチャンスは十分あります。
他業種と一括請負する際に注意することは?
たとえば、内装+電気+解体工事といった複数業種が絡むリフォーム工事を一括で請け負う場合、内装仕上工事業の許可だけでは対応できないことがあります。
請負金額が税込500万円以上になると、各業種ごとの建設業許可が必要です。
自社に許可がない場合は、許可を持つ下請業者に依頼することも可能ですが、元請として施工管理責任を果たさないと「丸投げ」とみなされる恐れもあります。
丸投げは建設業法違反に該当しますので注意が必要です。
また、契約書には工事範囲・金額・工期・責任分担などを明確に記載し、施工体制を明確にしておきましょう。
個人事業主で内装工事を始めるには?
個人で内装工事を始めるには、まず税務署に開業届を出して事業をスタートさせます。
工事の金額が税込500万円以上になる場合は、「内装仕上工事業」の建設業許可が必要です。
元請けとして、下請けや一人親方に作業を依頼することもできます。
ただし、工事全体を適切に管理しないと「丸投げ」とみなされ、法律違反となる可能性があります。
契約書には工事の内容や金額、工期、責任の分担などをしっかり書いておくことが大切です。
帳簿の管理や確定申告など、経理面の準備も忘れずにしておきましょう。
個人事業主として事業を安定して続けるためには、技術だけでなく、法令やお金の管理も大切です。