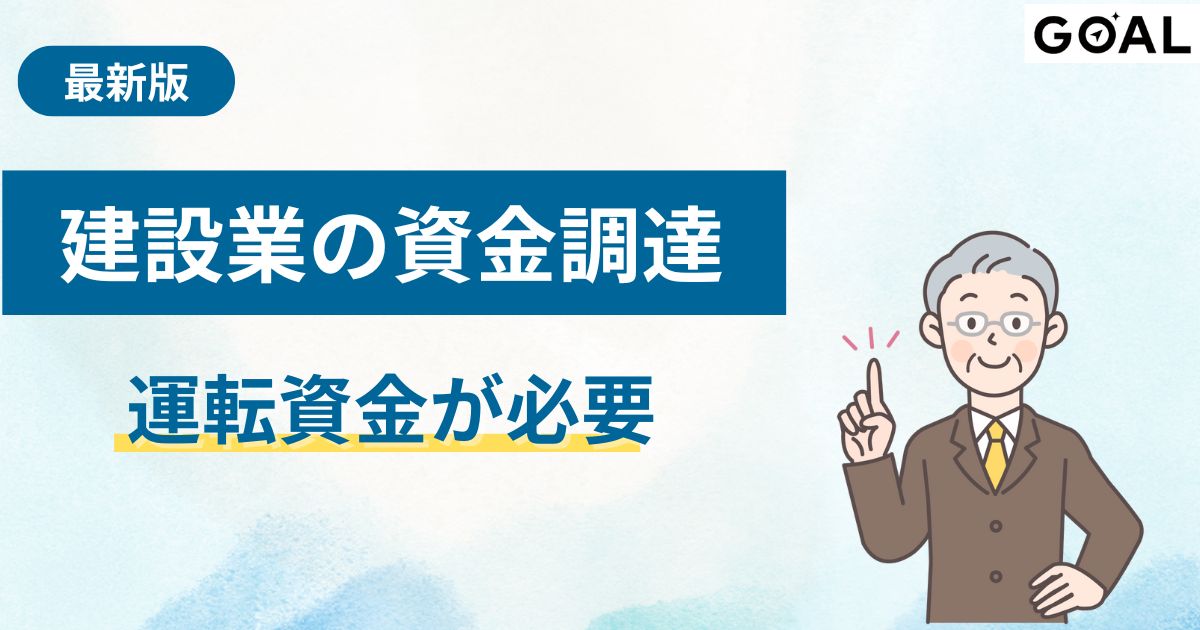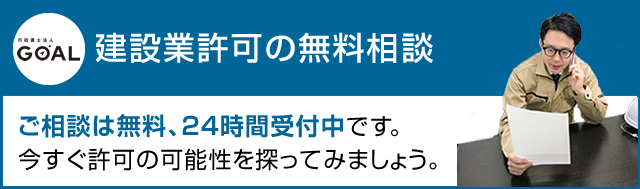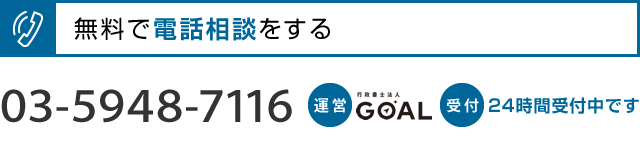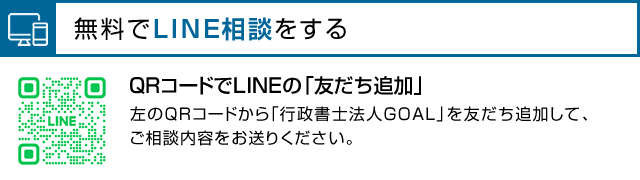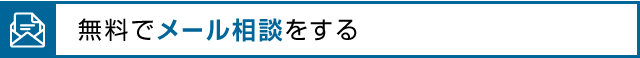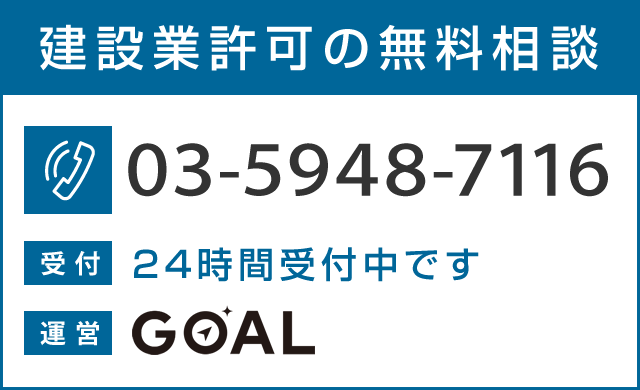建設業は、契約から代金の入金までに時間がかかりがちな業種でありながら、材料費や人件費など多額の支出が発生するという特徴があります。
特に建設業許可が必要な500万円以上の工事を請負際には多額の資金が必要です。
そのため、日々の運転資金に悩む経営者の方も少なくありません。
今回は、建設業における資金調達の重要性と具体的な方法、さらに資金繰りを改善するための実践的なポイントをわかりやすく解説します。
目次
建設業界における資金調達の重要性
建設業の資金調達は、「足りなくなってから」ではなく「足りなくなる前」に動くことが重要です。
そして業界特有の構造を理解し、資金調達の方法を日頃から準備しておくことが大事になります。
特に中小企業にとっては、資金繰りの安定が経営の要ともいえる課題です。適切なタイミングで資金を調達し、柔軟に運転資金を確保することが、競争力の維持や成長の鍵を握っています。
まず建設業界における資金調達の特徴とはどのようなものなのか解説していきましょう。
請負代金の入金サイトが長い
建設業界の特徴の一つが、請負代金の入金までの期間、いわゆる「入金サイト」の長さです。
建設業の多くは、工事の着手から完了までに数ヶ月を要し、工事完了後に検収・請求書発行・入金と進むため、実際の入金までには数ヶ月以上かかるケースも珍しくありません。
特に中小の建設会社や一人親方にとっては、工事完了までの間に発生する材料費や外注費、従業員の給与などの支払いが先行するため、手元資金が枯渇しがちになります。
結果として、利益は出ているのに資金不足で倒産(黒字倒産)というリスクも現実味を帯びてくるのです。
材料費や人件費が高騰している
近年、建設業を取り巻く経済環境は厳しさを増しています。
ウッドショックや原油高騰、半導体不足など世界的な供給制約により、建設資材の価格は高止まりを続けています。
それに加えて、人手不足を背景にした人件費の上昇も避けられず、現場運営に必要な費用は年々膨らんでいます。
また、建設業では労災保険や社会保険の負担も大きく、日々の運転資金に重くのしかかってきます。
経営者にとっては、資金のやりくりと安全で高品質な施工体制の維持を両立させるという難題に直面しているのが現実です。
このような状況下で工事を円滑に進めるには、早め早めの資金調達が必要不可欠です。
自社の経営を安定させるためにも、「どこから、どうやって」資金を調達するかを知っておくことは経営者にとってとても重要な経営判断のひとつです。
建設業の資金調達方法8選
建設業者が活用できる資金調達方法をまとめてご紹介します。
| 資金調達方法 | 特徴 |
|---|---|
| 日本政策金融公庫 | 低金利で長期返済ができる |
| 信用金庫・地方銀行 | 審査が柔軟でプランが豊富 |
| メガバンク | 金利が低く巨額の融資が可能 |
| 民間のビジネスローン | 担保不要で即日入金もできる |
| ファクタリング | 保証人不要で手続きが簡単 |
| 請求書カード払い | 手数料が安く支払いの先延ばしができる |
| リースバック | 即資金化でき税制対策もできる |
| 資産の現金化 | 会社の資産を現金化し投資に活用できる |
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫(通称「公庫」)は、国が100%出資する金融機関です。主に中小企業や個人事業主を対象とした融資制度を多数取り扱っています。
運転資金としても設備資金としても利用でき、無担保・無保証人で借りられる制度もあります。
建設業においては、新たな現場への着手時の運転資金や建設機材の購入資金など、さまざまな用途で利用されています。
公庫の主な融資制度は次のようになります。
- 新創業融資制度
- 普通貸付(運転資金・設備資金)
- 挑戦支援資金(中小企業経営力強化資金)
「新創業融資制度」は、創業間もない事業者や実績が少ない方にも開かれた制度であり、多くの建設業者が利用しています。
公庫を利用する際のメリット・デメリットについても確認しておきましょう。
- 低金利で借りられる
- 審査が比較的柔軟
- 担保・保証人が不要な制度もある
- 長期返済が可能
- 申込から融資まで時間がかかる(1〜2ヶ月)
- 書類作成が煩雑
信用金庫・地方銀行
地域密着型の金融機関である信用金庫や地方銀行も、建設業者の資金調達先としてもよく利用されています。
地域経済への貢献度や事業実態を評価して融資を判断するため、長年地元で営業している建設会社にとっては有利に働くケースもあります。
融資には顧客との継続的な関係性が重視されることもあり、審査が柔軟に行われる傾向にあります。
信用金庫や地方銀行を利用するポイントは以下のようになります。
- 保証協会付き融資が受けやすい
- つなぎ融資や短期融資も相談可能
- 審査が厳しい
- 中小企業は融資対象外の場合もある
取引実績がある銀行に相談すると迅速に対応してくれる可能性が高まりますので検討してみるのもよいでしょう。
メガバンク
支店によっては建設業専門の融資担当がいる三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行などのメガバンクも選択肢のひとつです。
信用力の高い企業や大規模案件を受注している建設業者であれば、安定した資金調達が見込めます。
大規模な建設プロジェクトに関与している企業や、複数の公共工事を請け負っている業者などに向いています。
メガバンクは金利が低めで、数億円規模の融資が可能です。
- 大口融資が可能
- 金利が低め
- 審査が厳しい
- 中小企業は融資対象外の場合もある
経営の規模が大きく実績がある中堅以上の建設業者向けといえるでしょう。
民間のビジネスローン
銀行融資が難しい場合、ノンバンク系のビジネスローンを活用するのも一つの手段です。
近年はWEB申込みや最短即日入金可能なサービスもあり、スピードを重視する事業者に人気です。
急な現場対応や資金ショートのリスクを減らすのにも役立ちます。
ビジネスローンを利用する際には下記の点にも注目しましょう。
- 赤字であっても利用できる
- 審査が早く柔軟
- 担保不要のケースが多い
- 金利が高い
- 返済期間が短い
- 審査基準が明確ではない場合もある
- 手数料がかかる
一時的なつなぎ資金として活用するには便利ですが、長期的な資金繰りには慎重になる必要があります。
ファクタリング
ファクタリングは、売掛債権(請求書)をファクタリング会社に売却して現金化する資金調達方法です。
融資とは異なり、借入金として計上されないため、信用情報や借入枠への影響が少ないのが特長です。
元請けに知られずに利用できる2社間ファクタリング、元請の承諾が必要になる3社間ファクタリングがあります。
- 必要書類が少ない
- 即日〜数営業日で現金化
- 赤字や債務超過でも利用可能
- 担保や保証人が不要
- 売掛金が即現金化できる
- 手数料が高い(2〜20%)
- 審査に通過しないことがある
- 悪質業者に注意が必要
近年は建設業に特化したファクタリング会社も増えており、信頼できる業者を選べば有効な手段になります。
請求書カード払い
請求書カード払いとは、材料や資材の購入時に請求書支払いをクレジットカードで立て替えるサービスです。
カード会社が先に支払い、事業者は後日まとめて支払う仕組みで、支払い猶予期間を確保できます。
材料費・資材費・重機レンタル費の支払いに利用し、その支払いを最大まで伸ばしたりもできます。
最近では、建設業に特化したカード払い代行業者も登場しています。
ただし、信頼できる運営会社かを確認し、導入前に手数料体系・遅延損害金の有無を調べたほうがよいでしょう。
請求書カード払いを利用する際のメリットとデメリットは次のようになります。
- 即日利用が可能
- キャッシュフローの改善ができる
- 支払いサイトの延長
- 支払先の変更は不要
- 手数料(2〜5%)がかかる
- カード枠に制限あり
支払いタイミングを調整したい建設業者にとっては非常に便利です。
リースバック
リースバックとは、会社が保有する建機や車両、不動産などを一度売却し、その後リースとして再利用する手法です。
資産を売却して即座に資金化できるうえ、業務は継続できます。
建設業界などで使われることが多く、「リース」と「ローン」の中間的な性格を持っています。
車両や建設機械などをリース会社が購入し、売却した事業者が借りる形で利用します。そして事業者は月々のリース料を支払うことで、実質的に購入するのと同様の効果を得られる仕組みです。
- 即資金化が可能
- 税務上のメリットもある
- 長期的にはコスト増
- 資産を手放すリスク
リース料は経費計上できるため、節税につながることがあります。ただし、長期的に見ると支払い総額は高くなる場合が多くなります。
資産の現金化
会社が保有する不動産などの資産を売却し、現金化する方法もあります。
特に、十分に活用できていない不動産や遊休資産がある場合、売却によって流動性の高い資金に換え、他の事業投資や運転資金として活用することが可能です。
近年は不動産価格も上昇傾向にあるため、想定より高い価格で売却できるケースもあります。
まずは、GMO不動産査定といった不動産一括査定サービスを活用して相場を確認しておくとよいでしょう。
建設業向け資金繰り改善のポイント
資金繰りに悩む事業者にとって大事なのは、資金調達だけに依存するのではなく、「資金を回せる経営体質を作る」ことです。
地道な経営努力が資金ショートを防ぐ最善策となります。ここでは資金繰りを改善するためのポイントを解説していきます。
資金・入金サイトの見直し
建設業において、入金サイトの長さはキャッシュフローに大きな影響を及ぼします。
発注者側の支払いタイミングに依存してしまいがちな請負契約ですが、交渉の際にはちょっとした心がけをすることも必要です。
たとえば着手金をもらう交渉の際には、工事前に一部の金額を受け取ることで、資材調達や仮設工事にかかる初期費用がまかなえます。
中間金の設定の際には工事の進捗に応じて段階的に入金を受けることで、完成までの期間中も一定のキャッシュを確保できます。
また、公共工事では国の前払金制度により契約額の一部(最大で契約金額の40%)を工事着手前に受け取れる「前払金」の仕組みが整備されています。
入金サイトの短縮は、実際のキャッシュインの早期化に直結するため、金融機関からの借入に依存しない経営体質を作る第一歩になります。
また資金繰りの基本は「いつ入金され、いつ支払いが発生するか」を把握することです。
受注前に入金サイトを確認し、可能であれば着手金や中間金を契約に盛り込むことで、資金繰りの改善が期待できます。
コスト管理と見積精度の向上
資金不足に陥る原因のひとつが「見積の甘さ」です。
資金繰りの改善には、収入を増やすだけでなくコストを適切に抑える工夫が必要です。
そのために正確な見積もりと原価管理が重要になるのです。
具体的には以下の観点で見直しをしましょう。
- 過去工事の実行予算と実績の比較
見積時と実行時の差異が生じた理由を明確にし、再発防止の対策を立てる - 外注比率の最適化
協力業者との契約単価や請求内容をチェックし利益の圧迫を防ぐ - 適正な利益率の確保
材料原価・人件費・現場経費だけでなく、管理部門の固定費や利益もしっかりと見積もりに反映させる
工事利益を確保できれば、それが運転資金の余裕にもつながります。
受注すればするほど苦しくなる状態から脱却するためには、見積精度を向上させることが欠かせません。
現場ごとの実行予算と見積金額が乖離しないように、過去実績をもとに材料費・人件費・外注費の見直しをし、利益率を確保しましょう。
また、無駄なコストを省き、利益が残る体質をつくることが重要です。
毎月の資金繰りの管理
多くの建設業者は、忙しさに追われて日々の現場運営に集中し資金繰りの把握が後回しになってしまいがちです。
しかし、資金ショートを防ぐには、未来をみすえた資金繰り予測が不可欠です。
例えば資金繰り表を作成し、入金・出金を「日別」「週別」「月別」で管理し、今後のキャッシュの流れの見える化をするのも有効です。
Excelや会計ソフトでも簡易的な資金繰り表は作成可能です。
建設業は月によって売上や入金額に差が出やすいため、月次の資金繰り表を作成して収支の見える化をしましょう。
また、定期的に経理担当や現場管理者と資金繰りの状況を共有し、工事ごとの収支と今後の見通しをするのもよいでしょう。
さらに普段から資金繰りの状況を銀行に報告し、早期に支援を仰げる関係性を築くこともいざというときの資金調達の迅速化につながります。
このように定期的にキャッシュフローを確認し、数ヶ月先の資金残高を予測することで、余裕を持った資金調達が可能になります。
建設業の資金調達に関するよくある質問
最後に、建設業の資金調達に関するよくある質問をご紹介します。
運転資金とはなんですか?
運転資金とは、事業を継続する上で日常的に発生する費用をまかなうための資金です。
建設業で発生する主な運転資金の内訳は以下の通りです。
- 資材・建材の購入費
- 外注業者への支払い
- 従業員の給与・賞与
- 現場交通費・ガソリン代
- 現場用工具や備品の購入
- 社会保険料・税金
こうした支出は、売上(=工事代金)の入金前に発生することが多いため、工事が増えるほど資金繰りが悪化するという事態にもなり得ます。
建設業において運転資金の確保は、とても重要な要素となります。
また融資の使途として運転資金と書かれていることも多いのが建設業の特徴です。
赤字でも資金調達はできますか?
赤字決算であっても、資金調達は不可能ではありません。
以下のような状況や工夫があれば、金融機関や民間ファイナンスの支援を受けられる可能性があります。
「今後数ヶ月で数千万円規模の工事受注が決定している」
「公共工事の元請契約がある」
など、たとえ直近の決算が赤字であっても将来的な売上の裏付けがあれば、金融機関側もポジティブに評価します。
「なぜ赤字になったのか?」
「どう改善しようとしているのか?」
「どのような収支計画を立てているのか?」
これらを説明できる「経営改善計画書」があると、融資審査が通る確率が大きく上がります。